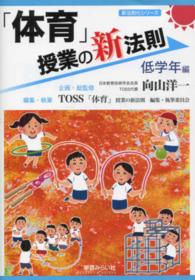出版社内容情報
感動とはなにか。読後の「心地よさ」に抵抗して、その「感動」の正体を探る。雑誌『日本児童文学』編集長でもある著者が、「児童文学」への批評的な関心により執筆してきた、書きおろしを含む21篇を収録(シリーズ第二巻)。
感動とはなんだろうか。読後の「心地よさ」に抵抗して、その「感動」の正体を探る。雑誌『日本児童文学』編集長でもある著者が、「児童文学」への批評的な関心により執筆してきた、書きおろしを含む21篇を収録(シリーズ第二巻)。
I 九〇年代からゼロ年代へ
1 いわゆる「ボーダーレス」作品の言葉をとらえる試み――<ばなな的香織のことば>を中心に
2 戦後五〇年・児童文学の対<子ども>意識メモ
3 「共感」の現場検証――『夏の庭』『宇宙のみなしご』『西の魔女が死んだ』に感動したあなたへ
4 透明な不安から身体の手応えへ
5 生き残りの生き方
6 再び地に足をつけるゼロ年代児童文学への期待――続・透明な不安から身体の手応えへ
II 意識的に読む
7 「児童文学」の「意識」としての児童文学批評が児童文学を鍛えるということについて
8 総天然色の人生とセピア色の悲しみ――<生きる>の書き手、日比茂樹
9 外へ「放す」こと――あるいは「語り」への信頼
10 <自然>指向の甘いわな
11 終わらない・終わりたい・終わる・終わればぁ?――現代日本児童文学「終わり」考
12 実感体感「歯型」考
13 厳然 VS もやもや――岩瀬成子作『朝はだんだん見えてくる』×伊藤遊『えんの松原』
III 「世界」と児童文学の間で考える
14 児童文学は「わたし」と世界をつなげるか――「加藤典洋」を児童文学論として読む
15 『わたしたちのアジア・太平洋戦争』体験から児童文学を考える
16 『あのころはフリードリヒがいた』『弟の戦争』合評研究会後記
17 『まぼろしの犬』おわりの発言
18 戦争児童文学を概観する
19 もしもしと呼びかけ続けて――『りかちゃんの国語科通信』(梨の木舎)という伝え方
20 上橋菜穂子『獣の奏者』を新しい戦争児童文学として読む
21 子どもの貧困にきく児童文学
【著者紹介】
『日本児童文学』編集長、「子どもの本・九条の会」運営委員。
1961年宮崎県高千穂町生まれ。86年、東京学芸大学大学院修士課程修了。著書に『りかちゃんの国語科通信―出産、子育て、南米の旅の巻』(梨の木舎 2008年)。共編著書として『わたしたちのアジア・太平洋戦争』全三巻(童心社 2004年)など。
内容説明
「心地よさ」に抵抗し「感動」の正体を探る。
目次
1 九〇年代からゼロ年代へ(いわゆる「ボーダーレス」作品の言葉をとらえる試み―“ばなな的香織のことば”を中心に;戦後五〇年・児童文学の対“子ども”意識メモ;“共感”の現場検証―『夏の庭』『宇宙のみなしご』『西の魔女が死んだ』に感動したあなたへ ほか)
2 意識的に読む(「児童文学」の「意識」としての児童文学批評が児童文学を鍛えるということについて;総天然色の人生とセピア色の悲しみ―“生きる”の書き手、日比茂樹;外へ「放す」こと―あるいは「語り」への信頼 ほか)
3 「世界」と児童文学の間で考える(児童文学は「わたし」と世界をつなげるか―「加藤典洋」を児童文学論として読む;『わたしたちのアジア・太平洋戦争』体験から児童文学を考える;『あのころはフリードリヒがいた』『弟の戦争』合評研究会後記 ほか)
著者等紹介
西山利佳[ニシヤマリカ]
『日本児童文学』編集長、「子どもの本・九条の会」運営委員。1961年宮崎県高千穂町生まれ。86年、東京学芸大学大学院修士課程修了。関英雄記念評論・研究論文(日本児童文学者協会)入選(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
純子
菱沼
kozawa
-

- 和書
- 文学とは何か