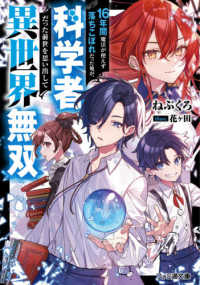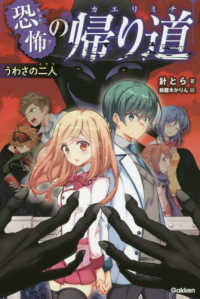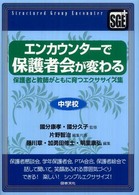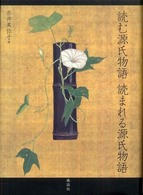出版社内容情報
気鋭の若手研究者による日本語文法史研究の論文集。現代語の理論研究や方言データなどから得た新しい知見をふまえ、実態をダイナミックに観察・記述するだけではなく、それに「説明」を加えることを試みた意欲的な一冊。
気鋭の若手研究者による日本語文法史研究の論文集。「現代語の理論研究や方言データも視野に入れた幅広い視点から研究を行うこと」「各時代語を中心としながらも、一時代の共時的な観察・記述にとどまらない歴史変化をダイナミックに描くこと」「どのような記述が歴史変化を「説明」するものとして必要十分であるか、自覚的に取り組んでいくこと」を目指して書かれた意欲的な一冊。
1. 古代の助詞ヨリ類―場所格の格助詞と第1種副助詞―
小柳智一
2. 「受身」と「自発」―万葉集の「(ら)ゆ」「(ら)る」について―
仁科明
3. 推移のヌ
福沢将樹
4. 指示詞系接続語の歴史的変化―中古の「カクテ・サテ」を中心に―
岡崎友子
5. タメニ構文の変遷―ムの時代から無標の時代へ―
吉田永弘
6. ~テイルの成立とその発達
福嶋健伸
7. 近代語のアスペクト表現についての一考察─ツツアルを中心に─
竹内史郎
8. 述部における名詞節の構造と変化
青木博史
9. 江戸語の推定表現
岡部嘉幸
10. 名詞キリの形式化と文法化
宮地朝子
解説 江口正
【著者紹介】
青木 博史(あおき ひろふみ)
1970年生まれ。九州大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員,京都府立大学文学部講師,助教授を経て,現在,九州大学大学院文学研究科准教授,国立国語研究所客員准教授。著書・論文に『語形成から見た日本語文法史』(ひつじ書房,2010),『ガイドブック日本語文法史』(共編著,ひつじ書房,2010),「名詞の機能語化」(『日本語学』29-11,2010)などがある。
内容説明
日本語文法の歴史変化をダイナミックに描く。実態の観察・記述だけでなく、そこに現代語研究からの知見もふまえた「説明」を加えることを試みた、幅広い視点での歴史的研究。
目次
1 古代の助詞ヨリ類―場所格の格助詞と第1種副助詞
2 「受身」と「自発」―万葉集の「(ら)ゆ」「(ら)る」について
3 推移のヌ
4 指示詞系接続語の歴史的変化―中古の「カクテ・サテ」を中心に
5 タメニ構文の変遷―ムの時代から無標の時代へ
6 ~テイルの成立とその発達
7 近代語のアスペクト表現についての一考察―ツツアルを中心に
8 述部における名詞節の構造と変化
9 江戸語の推定表現
10 名詞キリの形式化と文法化
著者等紹介
青木博史[アオキヒロフミ]
1970年生まれ。九州大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、京都府立大学文学部講師、助教授を経て、九州大学大学院文学研究科准教授、国立国語研究所客員准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。