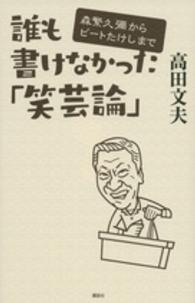内容説明
この巻では、神戸から名湯で名高い有馬、そして三田へと路線を延ばし、更に要の地点・鈴蘭台から分岐して、三木・小野・粟生など東播地方とも便利に結ぶ神戸電鉄の全てを紹介する。
目次
現在の車両(3000系(4両固定編成アルミカー)
1350形(3扉冷房装置付き通勤車)
1300形(両開き2扉通勤車) ほか)
思い出車両(デ1形;デニ11形;デ101形 ほか)
運行形態と施設(列車運行管理と施設;運行形態と列車種別;神戸電鉄の地形と勾配 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えすてい
7
神鉄の前面展望動画を見たことがあるが、確かに急勾配でカーブもあり、単線区間も少なくないから、スピードはお世辞にも「速くはない」。準急・急行も鈴蘭台以遠は事実上の各駅停車。朝の特快速だけが「速達列車」。カラーブックスとともに刊行当時は宅地開発が盛んで利用客増が見込まれたが、沿線人口の高齢化とバスの利便性向上で、神鉄は相対的に不利な状況となる。北神急行が市営地下鉄となって運賃が下がったが、それは神鉄にとってプラスになり得るだろうか?赤字が危機的な粟生線は存続できるだろうか?2021/02/26
えすてい
7
1050形と1070形という車両があった。主にラッシュ時の増結用で、1050形は2扉で片方が簡易運転台で構内での自走が可能。床下スペースが限られるため都営三田線6000形とともに日本初のSIVを搭載した車両。1070形は3扉で両運転台で自動解結装置付き密着連結器を片方に搭載。こちらも床下スペースの都合上SIV搭載。1050形は構内自走用簡易運転台とのことだが、これは鈴蘭台車庫で組成するためだけなのだろうか?途中駅で自走して連結・解結することはあったのだろうか?1050形は全廃され現存せず。2021/02/24
えすてい
6
カラーブックスでは分かりにくかった1000形スタイルの車両の「違い」が、私鉄の車両を読むと少しずつ分かるようになってきた。2扉車と3扉車の年次や形式の違い、増結用の車両などだ。カラーブックスの方は神戸電鉄自身で執筆してるので、どうしても「分かってるはず」で書かれている文体であること・文庫本サイズなので文字数や写真の掲載に限りがあることも大きい。私鉄の車両を見ると、カラーブックスも少しずつ分かるようになってきた。私鉄の車両シリーズは偉大だ。2021/02/23
えすてい
1
「神鉄編集委員会」による社史の色が濃いカラーブックス版「神戸電鉄」とは一線を画し、「私鉄の車両」に相応しい車両紹介に特化した内容。また、刊行当時の保育社らしい。カラーブックス版では触れられなかった複線区間/単線区間・準急/急行停車駅が記載されている。一方で車両紹介に特化しているので、カラーブックス版にはある神鉄の歴史・不動産開発・神鉄ビル・保養所、そして当時の皇太子・皇太子妃両殿下ご乗車記録には触れられていない。2018/02/27