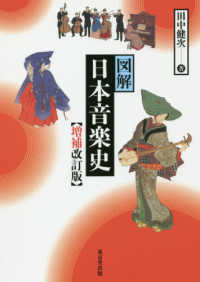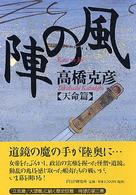出版社内容情報
さまざまなALifeのモデルをPythonで書かれたサンプルコードで実装することで、理論モデルを体感的に学ぶことができる書籍世界で初めての実装を通してALife(人工知能)を学ぶ書籍!
生命性をコンピュータ上でシミュレートすることにより、生命の本質に迫る「ALife」は、人工知能(AI)の発展系として近年改めて注目されつつある研究分野です。その応用先は、デザイン、ケ゛ーム、SNS、アート、建築と、人間の創造性が必要となる領域全般に及びます。本書は、さまざまなALifeのモデルをPythonで書かれたサンプルコードで実装することで、理論モデルを体感的に学ぶことができる書籍です。
岡 瑞起[オカ ミズキ]
著・文・その他
池上 高志[イケガミ タカシ]
著・文・その他
ドミニク チェン[ドミニク チェン]
著・文・その他
青木 竜太[アオキ リュウタ]
著・文・その他
丸山 典宏[マルヤマ ノリヒロ]
著・文・その他
内容説明
本書は、セルラーオートマトンやボイドモデルなど、さまざまなALifeの理論モデルを、Pythonで書かれたサンプルコードで実装することで体感的に学ぶことができるユニークな書籍です。雑多な情報を整理して「最適化」する力に優れたAIと比較して、「新たな自然を作り出す」という特徴を持つALifeは、人間の多種多様な創造的行為を支援すると考えられ、その応用先は、デザイン、ゲーム、アート、建築など、創造性が必要となる領域全般に及びます。機械学習の技術も活用するALifeを学ぶことは、AIをすでに活用している読者にとっても、発想を拡げるきっかけになることでしょう。
目次
1章 ALifeとは
2章 生命のパターンを作る
3章 個と自己複製
4章 生命としての群れ
5章 身体性を獲得する
6章 個体の動きが進化する
7章 ダンスとしての相互作用
8章 意識の未来
付録
著者等紹介
岡瑞起[オカミズキ]
工学博士。筑波大学システム情報系准教授、ウェブサイエンス研究者。United World College of the Adriatic(UWCAD)卒業、筑波大学大学院システム情報工学研究科博士課程修了。東京大学・知の構造化センター特任研究員、筑波大学助教を経て、現職。ウェブの存在そのものを新しい「自然現象」としてとらえ、その「生態系」としての構造を明らかにする研究を行う。また、2016年7月に池上高志・青木竜太と「ALIFE Lab.」を立ち上げ、ALifeの研究者と他分野との共創を促進する活動を展開中。専門は、ウェブサイエンス、人工生命。人工知能学会・ウェブサイエンス研究会主査。株式会社オルタナティヴ・マシン代表取締役
池上高志[イケガミタカシ]
理学博士。東京大学大学院総合文化研究科教授、複雑系科学・ALife研究者。1961年生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院理学系研究科博士課程修了後、米国ロスアラモス国立研究所に留学。神戸大学大学院自然科学研究科助手、東京大学大学院総合文化研究科助教授、オランダ・ユトレヒト大学理論生物学招聘研究員、東京大学大学院総合文化研究科教授などを経て、2010年より現職。複雑系と人工生命をテーマに研究を続けるかたわら、アートとサイエンスの領域をつなぐ活動も精力的に行う
チェン,ドミニク[チェン,ドミニク] [Chen,Dominique]
学際情報学博士。早稲田大学文化構想学部准教授、起業家・情報学研究者。1981年生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)Design/MediaArts学科卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。NTT InterCommunication Center(ICC)研究員/キュレーターを経て、NPOコモンスフィア(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)理事。株式会社ディヴィデュアル共同創業者・取締役。2008年IPA未踏IT人材育成プログラム・スーパークリエイター認定。ウェルビーイングとテクノロジーの関係、人工生命技術と創造性の関係性、インタフェース・デザインの研究活動に従事
青木竜太[アオキリュウタ]
コンセプトデザイナー、社会彫刻家。ヴォロシティ株式会社代表取締役社長、株式会社オルタナティヴ・マシン代表取締役「TEDxKids@Chiyoda」設立者兼キュレーターや「Art Hack Day」、「The TEAROOM」、「TAICOLAB」、「ALIFE Lab.」の共同設立者兼ディレクターも兼ねる。アートやサイエンス、カルチャー領域で、コンセプトデザイン、ディレクション、プロジェクトのプロデュースや事業開発を行う
丸山典宏[マルヤマノリヒロ]
東京大学大学院総合文化研究科特任研究員。1984年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科単位取得満期退学。同大学院池上高志研究室でALife分野の研究を行う一方、大学内外でアート作品制作や開発業務にハード・ソフト両面から主に技術スタッフとして携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。