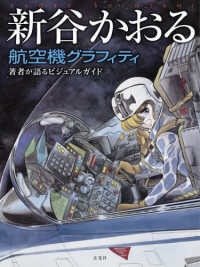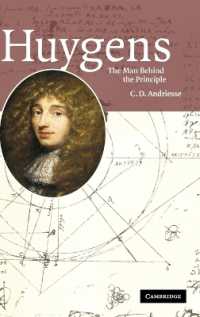内容説明
輸入している食料は外国の水で作られている。世界の水争奪戦は生活を直撃する。水源地や地下水は誰のもの?外国資本や企業の動きに自治体の水保全政策は有効か。水の危機は地域自立の危機。日本の水循環を問い直す。
目次
1 世界と日本の水課題
2 自治体の水道事業はなぜ海外を目指すか
3 海外水インフラPPP協議会
4 開発途上国にフィットした技術をBOPビジネスで展開する新潮流
5 雨水を活用し洪水対策、水資源確保を図る
6 地下水の利用と保全で悩む地方自治体
7 水循環基本法とはどんな法律か
8 地下水の見える化で水マネジメントが変わる
9 小規模コミュニティーには水道ソフトが必要
10 FEW(food、forest、energy、water)を自立するコミュニティー
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
香菜子(かなこ・Kanako)
36
水は誰のものか―水循環をとりまく自治体の課題 (自治体議会政策学会叢書/Copa Books)。橋本淳司先生の著書。水環境問題はほかの環境問題と同じように日本だけの問題ではない。水を巡った水戦争は古代からあったようだし、現代でも存在している。地球上のあらゆる場所で水戦争が頻発するような時代が来るのもそう遠くないのかも。水環境を人類全体で守る努力が必要。2018/12/28
Ryan
1
日本の土地が海外の企業や投資家に買われ始めているというニュースは聞いたことがありますが、彼らの狙いは日本の地下水。今の日本の法律では、土地を買ったら、そこの地下水は自由に汲み取ってもOKだということが驚きでした。いろんな自治体が地下水保全のための条例を作ってはいますが、国も何かしらのアクションが必要になってくるでしょう。そして、自分たちもいつも飲んでいる「水」に関心を持つことがまずは必要ですね。2015/05/03