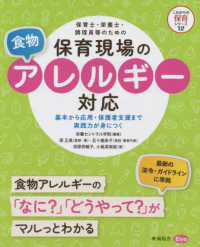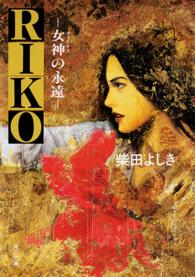内容説明
旧著『石鎚山と瀬戸内の宗教文化』(岩田書院刊、1997)、前著『武州御獄山信仰-山岳信仰と修験道(上)』(同、2008)に続き、日本の霊峰富士山と、相模大山信仰の実態を明らかにする。地域に生きる講、信仰を伝える御師・導者、参詣路・御師集落などについて、古文書・道中記などの史料、奉納物・宿帳・マネキなどの遺物、伝承などから、多角的に論究。
目次
富士講と御師―マネキの資料紹介をかねて
富士信仰の展開―信仰民具試論
富士山の山小屋と強力―近世から近代における山岳信仰の展開
富士導者の奉納物
峠を越えた富士の導者たち―南足柄立花屋宿泊人名簿をめぐって
葛飾区飯塚の富士講―一枚のマネキから
神奈川県開成町の富士講
山岳信仰と奉納物―近世以降の石造物を中心にして
富士山伝説
同行衆と富士登山―若者組の通過儀礼をめぐる史料紹介
小田原の道了尊信仰
平塚の平和講
相州大山講と蓑毛御師
守札にみる庶民信仰―屋根裏から発見された古札
片参り・山を割る考―伝承と文芸のはざまで
大山信仰の地域的展開
足柄道の交通交易をめぐって
著者等紹介
西海賢二[ニシガイケンジ]
1951年神奈川県小田原市生まれ。筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程修了。東京家政学院大学人文学部・大学院人間生活学研究科教授。法政大学・愛知大学大学院講師。NPO法人石鎚森の学校副理事長。博士(歴史学)・博士(民俗学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。