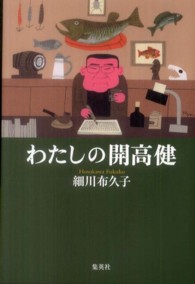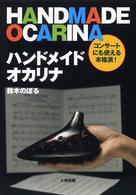内容説明
歴史が解釈にすぎないことは、ヨーロッパの歴史教育の基本である。かつて日本でも、このような視点から実践が試みられていた。本書は20世紀前半から現代までの、「解釈型歴史学習」の系譜を整理し、現代的意義と方法的特色を明らかにすることで、歴史認識の対立を乗り越える、市民と生徒のための歴史学習理論を探究する。
目次
序章 解釈としての歴史と本論の課題
第1章 国民国家形成期の日本の歴史教育―「国民」としてのナショナルアイデンティティーの形成
第2章 日本における市民社会成立期の解釈型歴史学習―1920年代の歴史教育実践の特質
第3章 国家主義歴史教育浸透期における解釈型歴史学習の限界―1930年代における歴史教育転換の論理
第4章 戦後日本における解釈型歴史学習―社会科としての解釈型歴史学習
第5章 変化する国民国家の中での解釈型歴史学習
第6章 歴史解釈の客観性―歴史教育における「鎖国」論を例に
第7章 解釈型歴史学習における主観の相対化―対話の役割
第8章 解釈型歴史学習における歴史家体験活動
終章 アジア共通歴史学習としての解釈型歴史学習の可能性
著者等紹介
土屋武志[ツチヤタケシ]
1960年長崎市生まれ。長崎大学教育学部卒業。上越教育大学大学院学校教育研究科修了。長崎県公立中学・高校・教育センター勤務の後、1995年愛知教育大学助教授。2006年同教授。2010年10月より岡崎市教育委員会委員を兼務(2013年10月委員長)。専門:社会科歴史教育・授業コミュニケーション、博士(学校教育学)。所属学会:日本社会科教育学会・全国社会科教育学会・日本生活科総合的学習教育学会・日本学校教育学会・日本NIE学会等(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。