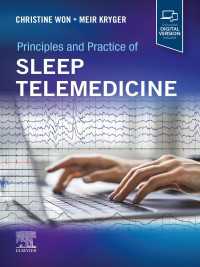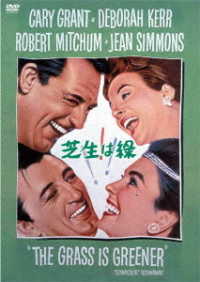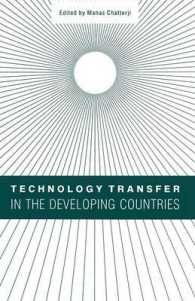内容説明
白黒つけたくない”日本人の法意識のありようを再検討する。勧解制度は、なぜ導入されたのか。どのように運用され、いかなる種類の紛争と関係していたのか。多くの紛争を処理していたにもかかわらず、なぜ廃止されたのか。このような制度面にかかわる疑問とともに、日本における裁判所制度の創設期に勧解が果たした役割とその評価といった思想面、前後の時代への影響について明らかにする。
目次
序章 勧解・調停を研究する視角
第1章 勧解制度の導入
第2章 勧解制度の施行―紛争解決制度形成過程における勧解前置の役割
第3章 勧解制度選好の要因
第4章 勧解制度の廃止
第5章 勧解から督促への変化
第6章 勧解と裁判との比較―明治前期の「雇人」事件を中心に
第7章 借地借家調停制度成立に至る経緯
第8章 一九三〇年代の金銭債務臨時調停制度の特徴
終章 ウラオモテの制度と「前段の司法」
著者等紹介
林真貴子[ハヤシマキコ]
1997年大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。PhD(ロンドン大学)。大阪大学法学部助手を経て、近畿大学法学部教授。専門は、日本法制史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。