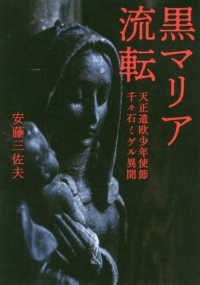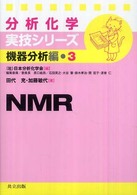目次
辞書・音義(太安万侶の訓詰学―原本系『玉篇』の利用についての試論;天治本『新撰字鏡』と法隆寺一切経;倭名類聚抄の道円本と十巻本;隋・唐代における字体規範と仲算撰『妙法蓮華経釈文』;掲出順位・俗注記等からみた二巻本『世俗字類抄』の同義異表記語;『浄土三部経音義集』所引の本草注の出典について;辞書・事典に連続する抄物群―詩文作成のための抄物の場合;下学集で「日本俗」などの注記のある語二、三;「十二韻」の韻書;萩原広道『古言訳解』の俗語訳と方言語彙;近代辞書の古語と文語―『和英語林集成』と『日本大辞書』をめぐって;古語辞書の意味記述―助動詞「む」の連体形について;動詞の辞書記述とアスペクト)
外国資料(日本語に於ける有気音と無気音―室町時代以後の中国資料による;『捷解新語』に於ける漢語―改修態度を中心として;『新スラブ・日本語辞典』の「オ」の表記;外国資料よりみた18世紀初頭の薩隅方言―助詞の融合について;『交隣須知』の筆写本と刊行本の日本語について〈「活用」篇〉;重刊改修捷解新語に見られる区切り小点について)
特別寄稿 蘭学者はどのように工夫して西洋語を音訳したか
大友信一博士略歴
大友信一博士著述目録