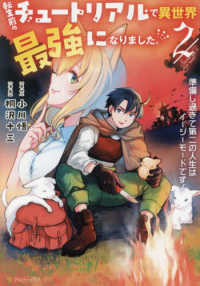目次
製本史に関する二つの疑問
くるみ製本
現在の製本様式調査
無線綴製本
切断無線綴
あじろ綴
フランス装の歴史
南京綴製本
針金綴製本
釘を使った製本と「装釘」
著者等紹介
大貫伸樹[オオヌキシンジュ]
1949年、茨城県那珂郡大宮町生まれ。東京造形大学デザイン科卒業。大貫デザイン事務所代表。日本出版学会会員。東京製本倶楽部会員。日本図書設計家協会会員。第38回造本装幀コンクールにて自ら執筆、装丁を手掛けた『装丁探索』が受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
28
ほとんどの現代の本は、接着剤を使った「無線とじ」で作られている。しかし、適した接着剤のなかった時代、開くと割れるような本もあった。現代の出版は接着剤の進歩と、改良された「あじろ綴じ」に助けられたというべきだろう。著者があじろ綴じ開発者の孫に出会うシーンは、まさに奇遇。この本自体は、昔ながらの糸とじで、さすが「製本の本」である。フランス装が敗戦後に多かったというのも歴史の必然を感じさせる。2016/12/28
paluko
8
「あじろ綴」「フランス装」に多くの紙数が割かれている。また装丁、装幀、装釘、装訂どの表記が正しいのか、もしくは意味の違いは? とか。表紙のオブジェも著者が作っているのですね。本の精神(テキスト)の電子化が進むにつれ、逆に本の身体(装本)の細部も、わざわざ紙の本を作る/買う場合には気になってくるのかもしれない。所蔵している都立図書館に、当該書の装釘について著者が問い合わせたときの行き届いた回答には感心した(117頁)。2023/10/20