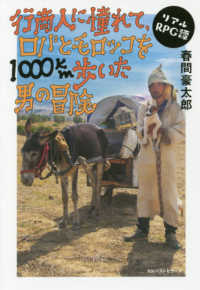内容説明
かりそめの繁栄の次に来るものはいったい何か。物にとらわれず豊かに生きる知的生活のすすめ。
目次
第1部 (私の生き方―買わずに拾う、捨てずに直す;地球から緑が消える;家畜には草、ペットには残飯を;地救原理の導入を;地球は私のもの、私は地救人)
第2部 (人にはどれだけのものがいるか―エネルギー・物質多消費文化への警告;国際化時代の環境問題;「地球化」を迫られる座標軸なき国家・日本)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
12
図書館本。世にある断捨離とかミニマリストの本とは違い、エコロジーな面からのモノの扱い方。自分には関係ないからではなく「地球は自分のもの」と思えば自ずと大切にする。戦前生まれの著者は「勿体ない」が体に染み込んでおり、物を長く大切にするというのが当たり前の時代を知っている(同世代が皆同じとは限らないが)。足るを知るとはこういうことかな。「人間は人間から遠いものほどよくわかる。人間から遠いものを扱う学問は信頼出来るが、学問は人間に近づいてくるほどインチキです。学説や常識がコロコロ変わる」なるほどな!と思った。2024/08/04
Mayu
9
TOEIC爺さん、の中で紹介されていた鈴木孝夫先生の本。この言語学者の方を今まで全然知らず、この本は恐らく先生の著作の中でも専門と関係のない話というか、かなり異質な物だと思うのですが、全面的に共感できる内容でした。大学の先生の断捨離本もあるのかな、なんて思って読み始めましたがそういう次元の話ではなく、誰もが口を揃えて言っている地球を守るためにできる限りのことをしましょう、ということを本当の意味で実践されている方かなと思いました。人間は自然の一部だという認識が、本当の幸せは何かという問いに答える鍵なのでは。2017/08/20
Charlie
5
結構古い本だけど今でも十分通用し、しかも現状はもっと悪化している為より切実感が増している。「もっと低い経済のレベル、消費の水準でも人間は幸福に生きられる」という一文ははっとさせられた。しかしタイトルずばりの回答が出ているわけでなく、終盤の講演・論文はいかにも学者の文章なため正直しんどい感も。2013/10/21
mayabooks
2
文庫版がでてるけど図書館に単行本があったのでそちらを読む。なんだか色々徹底していてすごい。こういう考えの人がもう少し多くなると無駄に買ったり捨てたりことも減るのかもしれない。少なくとも我が家では無理な気がする。2011/06/03
ナオ
0
◯2016/07/14