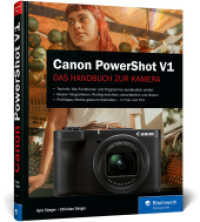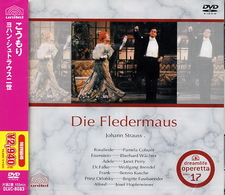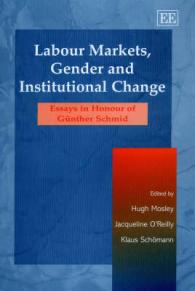内容説明
膨大な血と涙が流れた大地の記憶を発掘!加害者も被害者も、沈黙し続けてきた中国で受難者の足跡を、生涯をかけて尋ね歩く孤高の歴史家の調査記録とその分析。王友琴関係・文革三部作の完成。
目次
第1篇 恐怖の「紅い八月」
第2篇 生徒が先生を殴った革命:一九六六
第3篇 日記を壊した革命
第4篇 清華大学附属中高校の闘争モデル
第5篇 文革「闘争会」に関する調査と考察
第6篇 受難者の側から“反右派闘争”と“文革”との関連性を考える―北京大学を例として
第7篇 文革における『羅生門』的現象―北京大学が「林彪の娘を迫害した」といわれる事例について
第8篇 文革反省の一視角
第9篇 張春橋の亡霊が漂っている
第10篇 宗教信仰を持つ人々の受難記
附録 毛沢東独裁下、史上未曾有の飢餓地獄の記録(一九五九~一九六一年)裴毅然著『赤難史證(第八章「進入天童」)』
著者等紹介
王友琴[オウユウキン]
1952年生まれ。女性。北京師範大学附属女子中学に飛び級で入学(13歳)、この年に文革が始まる。中学在学中、1966年夏、紅衛兵運動に遭う。両親の出身階級が教師だったため身分が悪いと迫害された。まだ17歳にもならないのに14歳の妹と共に雲南省に下放され、6年間、貧苦の中でゴムの木を植えさせられた。後、北京大学中文系に合格、社会科学院で博士号取得の後、アメリカにわたり、スタンフォード大学、シカゴ大学で教鞭をとり、文革の実態調査と歴史研究を続ける
小林一美[コバヤシカズミ]
1937年長野県八ヶ岳南麓に生まれる。この年、スターリンの赤軍将校の大粛清、日本軍の上海攻撃、南京占領の虐殺事件が起きる。8歳の時、敗戦。以後、占領下で、落合村立落合小学校を経て諏訪清陵高校、東京教育大学で学ぶ。専門は世界史の理論と中国史研究。名城大学、神奈川大学の教師を勤める
佐竹保子[サタケヤスコ]
東北大学文学部卒。同大学院博士課程後期単位取得退学。博士(文学)。在学中に北京大学中国語言文学系高級進修生。東北学院大学、鳴門教育大学、東北大学大学院文学研究科を経て、現在、東北大学名誉教授・大東文化大学外国語学部特任教授。専攻は中国古典文学、漢魏六朝文学
土屋紀義[ツチヤノリヨシ]
1946年東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程中退。長年の国立国会図書館職員を退官後、大阪学院大学教授等を経て現在同大学名誉教授
多田狷介[タダケンスケ]
1938年茨城県に生まれる。1968年東京教育大学文学研究科博士課程(東洋史学専攻)単位取得退学。公益財団法人東洋文庫研究員、日本女子大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。