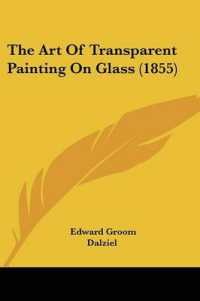内容説明
従来、日本の医療システムには高い評価が与えられてきたかもしれない。しかし、すでに現状は異なってきているのではないか?現状の医療は、多様で容易にアクセスできる質の高い医療などとは評価できないのではないか?そうだとすればそれは、これまで機能していたルールや考え方がうまく働かなくなっていると考えざるを得ないだろう。今回の新型コロナウイルスによるパンデミックへの対応の混乱ぶりは、この象徴である。そもそも医療は、人が生きていく中で必ず享受するヒューマンサービスのひとつである。その医療が閉塞状況にあるということは、取りも直さず、日本の社会の仕組みそのものが閉塞状況にあるということではないだろうか。これは、日本の社会そのものに内包していた欠陥が表面に見える形で現れているということである。医療の本質は複雑系であり、医療実践の基本は原価計算にある。複雑系の視点から医療の再興を考える。
目次
複雑系と病院原価計算の出会い
第1部 新たな視点で病院原価計算体系を創るための枠組み(病院原価計算を考えるにあたり―背景にある新たな健康観;病院経営と病院原価計算とを統合する基軸 ほか)
第2部 新たな病院原価計算方式(診療区分方式:診区方式)の呈示(病院原価計算を統合するマザーフレーム(mother frame)の呈示
新たな病院原価計算 診療区分方式(診区方式)の呈示 ほか)
第3部 医療における複雑系(線形、非線形、力学系、そしてカオス、複雑系へ;複雑系とベキ分布 ほか)
第4部 複雑系から医療へのメッセージ(主観にもとづく質の評価へ;病院に内在する複雑性 ほか)
資料集
著者等紹介
田原孝[タハラタカシ]
精神科医師、緩和ケア在宅診療医師、産業医理学博士、医学博士。1943年大分県生まれ。1966年九州大学理学部卒。1972年同大学院理学研究科博士課程修了。1981年大阪大学医学部卒。国立肥前療養所(現、国立病院機構肥前精神神経センター)、医療法人徳州会病院、その他の病院で臨床に携わると共に、九州大学、久留米大学、立命館大学、日本福祉大学、日本赤十字九州国際看護大学、東京大学など数々の大学や教育機関で教授等の教官を務める。この間、プライマリーケアをはじめとする臨床、および各種学会の役員や病院管理に従事しながら、診療録・医療情報システムの開発や導入、診療情報の開示、カオス・複雑系の研究等を行う。現在、臨床に携わりながら「医療・福祉基盤研究所」代表取締役として活動している
平井孝治[ヒライタカハル]
1942年京都市生まれ。1967年3月九州工業大学制御工学科卒。1969年3月九州大学工学研究科応用物理学専攻修士課程修了。その後九州大学工学部、名城大学商学部、立命館大学経営学部等の教官、教授を務める。数学基礎論を専門としながら数理会計学、公益経営学の新たな領域を拓き、最近はガン罹患率の数学的考察を行っている
日月裕[タチモリユタカ]
麻酔科医師、理学博士。1952年石川県生まれ。1975年京都大学理学部卒。77年同理学研究科退学。1981年大阪大学医学部卒。いくつかの病院に勤務後、市立豊中病院麻酔科に15年勤務する。豊中病院麻酔科部長時代より、病院情報システムの開発と研究に従事。その後、いくつかの病院にて、病院情報システムの導入とホスピスの立ち上げを行った後、2004年から2017年まで日本福祉大学教授として勤務。その間、医療の複雑系についての研究を行い、北海道大学にて理学博士(数学)を取得。現在は麻酔科の非常勤医師として働きながら医療の複雑系の研究を継続している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書
- In Homespun
-

- 和書
- 黒衣のダリア 文春文庫