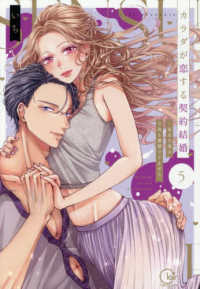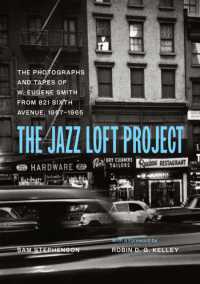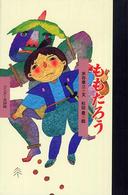内容説明
ピアノ製造の一大拠点だった浜松で、技術力で知られた大橋ピアノ研究所。「幻のピアノ」と呼ばれるピアノと職人たちの軌跡を追う。
目次
第1章 「いい音をいつまでも」(あるピアノ製作者の死とピアノ;日本のピアノ史概観;大橋幡岩とピアノ;オオハシピアノのこだわり;オオハシピアノの周辺―ベヒシュタインとディアパソンについて)
第2章 「OHHASHI」の音色を求めて―オオハシピアノとの出会い(アップライトピアノ編;グランドピアノ編;その他特別なピアノ;ディアパソンピアノ)
第3章 ピアノの仕組み(ピアノの仕組み)
付録 データ、資料編(“記録魔”大橋幡岩―浜松市博物館所蔵資料について;Nヤマハ製作資料及び納品先記録;キーワード集)
著者等紹介
長井進之介[ナガイシンノスケ]
国立音楽大学鍵盤楽器専修(ピアノ)卒業、同大学大学院修士課程器楽専攻(伴奏)修了を経て、同大学院博士後期課程音楽学領域単位取得満期退学。2013~14年にカールスルーエ音楽大学に交換留学。2015年度にはDAAD「ISK」奨学生としてライプツィヒに留学。2007年度柴田南雄音楽評論賞奨励賞受賞(史上最年少)。伴奏を中心とした演奏活動と共に、音楽ライターとして複数の音楽雑誌に定期的に寄稿。またCDライナーノーツの執筆及び翻訳(独/英語)なども行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
勝ちねこキキ
15
大橋幡岩の国産ピアノ製造・販売までの記録と、それに伴う国産ピアノの歴史的背景。ベヒシュタイン社から来日したシュレーゲルに学び、量より質を求め続けた大橋氏。当然、材質にもこだわり抜いた結果、20年も寝かせた木材もあったとか。後半はピアノという楽器の仕組みの話になるが、もっと大橋氏がこだわった部分や、何故ここまでの情熱を持ってピアノと向き合うことができたのか聞きたかった。途中で出てくるベヒシュタイン使用者の声は参考になるが、そのメンバーがなんともゴージャス!いつかどこかで大橋ピアノの音を聴く機会に恵まれたい。2024/08/03
ミルチ
8
親子二代に渡る日本のピアノ職人の記録。話には山葉も河合も出て来て興味深い。日本の手作りピアノの創生と衰退。私のピアノのメーカーも数年前に廃業してしまった。昔の日本には職人さんが永く使える良い物を情熱を賭けて作っていたのに、今や安くてすぐ壊れるものばかり作る国になってしまっているのがなんとも哀しい。 2019/07/12
tama
7
図書館本 地域の産業棚で発見 家ピアノの会社DIAPASONの前身なので 大橋ハタイワって読むって知らなかった。JAZZの先生もバンガンって言ってたし。今の磐田市の池田出身なのかあ。技術屋に経営をさせると、の諺通りの歴史だが、10年以上前に遠鉄電車の積志辺りの線路近くに建っていた工場に大きくDIAPASONって書いてあったのはどうなったか。kawaiの知り合いに聞いてみよう。youtube=https://www.youtube.com/watch?v=o-9hM0Cu_0g2021/11/07