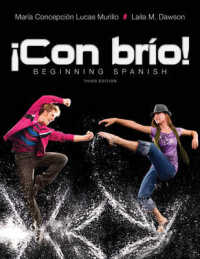- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
目次
プロローグ 愛着障害、愛着の問題についての正しい理解の大切さ
第1章 愛着障害の理解と支援のポイントを整理する(愛着形成のために三つの基地機能;発達障害と愛着障害を見分けるポイント ほか)
第2章 事例でわかる!「してはいけない」対応(こどもの感情に期待する対応をしてはいけない!;叱る対応や追い詰める対応がさらなる問題を引き起こす! ほか)
第3章 事例でわかる!「愛情の器」モデルに基づく愛着修復プログラムによる支援の実際(第1フェーズ 受け止め方の学習支援;第2フェーズ こども主体で大人主導の働きかけへの応答学習 ほか)
第4章 事例でわかる!発達障害と愛着障害を併せ持つこどもの支援(支援にさまざまな工夫が必要な第三のタイプの愛着障害;愛着障害のさまざまな現れ方とその支援)
エピローグ 支援の正しい順番を意識することの大切さ
著者等紹介
米澤好史[ヨネザワヨシフミ]
和歌山大学教育学部教授。臨床発達心理士、学校心理士スーパーバイザー、上級教育カウンセラー、ガイダンスカウンセラー。専門は臨床発達心理学・実践教育心理学(こどもの理解と発達支援・学習支援・人間関係支援・子育て支援)。学校園所等のこどもの現場に直接出向いて助言・支援している。日本教育カウンセリング学会理事、日本教育実践学会理事、「教育実践学研究」編集委員長、日本学校心理士会幹事、日本臨床発達心理士会幹事、関西心理学会役員(委員)、和歌山県教育カウンセラー協会会長、日本臨床発達心理士会大阪・和歌山支部幹事、和歌山市男女共生推進協議会会長、岸和田市子ども・子育て会議会長、岸和田市児童福祉審議会会長、摂津市子ども・子育て会議会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう
るい
motoryou
ヤナセトモロヲ
ぬぐみ
-

- 電子書籍
- VTuberなんだが配信切り忘れたら伝…