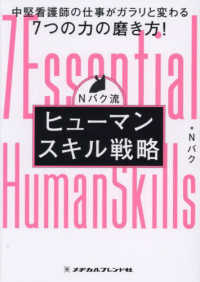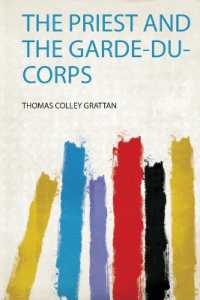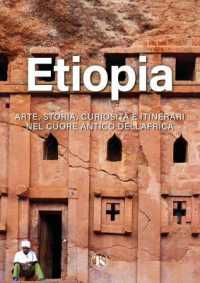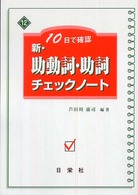出版社内容情報
衰退期に入った日本で内向きにならず、生きるのに楽しい社会をつくる模索が全国各地で。その最前線をサポートする著者の全力報告!生き心地のいい小さな社会が生まれている!
前作『農的な生活がおもしろい』から、さらに進化。衰退期に入った日本社会で、どうすれば自分の生活基盤を立て直すことができるか、居場所をつくることができるかを、各地に出向きサポートし、その現場(長野県飯田市、千葉県柏市、北海道富良野市、愛知県豊田市など)をレポート。人びとが孤立しあい、「生きる力」の育成ができないような社会に未来はない。円(カネ)よりも縁(つながり)が、一人ひとりが社会のフルメンバーとして生きる実感を感じられ、一歩でも前へ進む駆動力を発動させる。これからの日本社会のあり方を提案する問題作!
はじめに 見えない「つくる」をつくる
第1章 下り坂社会のただなかで
第2章 人とつながる、社会とつながる
第3章 一人ひとりが社会のフルメンバーとして生きる
第4章 小さな「社会」をたくさんつくる
牧野篤[マキノアツシ]
1960年、愛知県に生まれる。1988年、名古屋大学大学院教育学研究科博士課程を修了。名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授を経て、2008年より東京大学大学院教育学研究科教授。もともと近代中国教育思想ならびに社会教育・生涯学習が専門だが、それに加え、日本のまちづくりや高齢化・過疎化問題、多世代交流型コミュニティの構想と実践に取り組んでいる。
著書には『生きることとしての学び』『認められたい欲望と過剰な自分語り』(以上、東京大学出版会)、『シニア世代の学びと社会』(勁草書房)、『農的な生活がおもしろい』(さくら舎)などがある。
内容説明
いま生き心地のいい小さな社会が続々と各地で生まれている!人が戻りたくなる居場所をつくる!下り坂社会のただなかにあっても、人が心地よく暮らせる社会、地域をつくるための模索が全国各地でなされている。その最前線をサポートする著者が示す、これからの生き方!
目次
第1章 下り坂社会のただなかで(小さな国の衰退期;うら悲しさの内実 ほか)
第2章 人とつながる、社会とつながる(長い箸の寓話;呪いの言葉を掛けあう社会 ほか)
第3章 一人ひとりが社会のフルメンバーとして生きる(楽しく幸せに暮らすための日々の「学び」;貧困の連鎖にくさびを打つためにも ほか)
第4章 小さな「社会」をたくさんつくる(「消滅可能性都市」が流行語に;「地方消滅」がまきちらす心理 ほか)
著者等紹介
牧野篤[マキノアツシ]
1960年、愛知県に生まれる。1988年、名古屋大学大学院教育学研究科博士課程を修了。名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授を経て、2008年より東京大学大学院教育学研究科教授。もともと中国近代教育思想ならびに社会教育・生涯学習が専門だが、それに加え、日本のまちづくりや高齢化・過疎化問題、多世代交流型コミュニティの構築などにも取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
1.3manen
きいち
RYOyan
まっちゃん