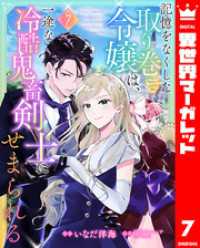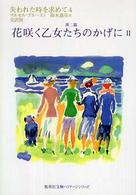出版社内容情報
はしがき
七分積金とは、町入用節減額の十分の七の積金と言う意味である。寛政三年松平定信は江戸の地主階級が負担する町費すなわち町入用を節減するため、天明五年より寛政元年まで五ケ年平均の町入用を算出させ、その額より出来る限り節約した町入用節減高を書出させて、節減を実行させ、その節減額の十分の七を備荒貯蓄のための積金並びに米穀購入費に充て、会所と籾蔵を向柳原に設立した。これが江戸の救済事業機関たる町会所であった。町会所は七分積金を取扱い、それによって備荒のための事務や市民の救済事業を行う事務所といえる。この町会所の設立によって江戸の市民が不時の災害から救われた数はおびただしいものであって、又一般貧困者も会所支給の米金によって大きな恩恵を蒙ったこと言う迄もない。江戸における社会救済事業の機関である町会所の事業が維新後の変動のため、どのように活用されるに至ったか、この金をとり扱う役所が営繕会議所より東京会議所となり、旧来の町会所の事業から一転して、営繕事業から教育事業にまであらゆる面にこの積金が利用されるように発展していった。市民の共有金という意味より、一般市民の福利事業がこの積金によって遂行されたこと及び災害のたびに米金を支給する事は救済の根本でなく、恒久救済施設の整備こそその根幹をなすものであるとの当局者の見解から、養育院、日雇会社、工作場の設立となって、当時政府及び府当局が最も悩んだ乞食浮浪者の処理対策に主役を演ずるに至った経過をのべ、この会議所によって着手された事業が、会議所廃止後東京府に引継がれてどのように運営されるに至ったか、府管理時代に至ってこの共有金はどんな方面に支出されたか等、積金が江戸より東京への変転に従って、その使用目的に於て、飛躍発展していった過程を一通り系統的にのべたのが、この小篇である。
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0604t_kiyo07.htm