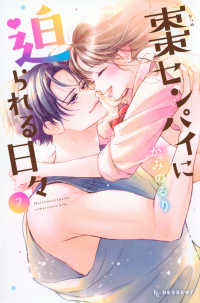内容説明
米、酒、新幹線、人口…。大丈夫か、新潟?でも心配無用!地方自治と食の専門家が、膨大なデータを駆使して愛すべき新潟の課題を分析。隠れたお宝を次々に発掘し、説得力抜群の具体策を提案する。
目次
第1章 気がかりな新潟―過去の「栄光」はいまいずこ(人口日本1からの転落;危うし日本1 ほか)
第2章 大丈夫か?新潟(新潟県はどこへ行く?;道州制論議の区割りでもはっきりしなかった新潟県 ほか)
第3章 実は隠れたお宝がいっぱい、それが新潟の実力だ!(新潟県は枝豆県?;新潟県は野菜王国だ! ほか)
第4章 新潟のまちの正しい磨き方(新潟県人は宣伝下手か;村上の光り輝くまちづくり ほか)
第5章 新潟の逆襲がいよいよ本気モードに(新潟オリンピックが正夢に;右肩上がりのインバウンド ほか)
著者等紹介
田村秀[タムラシゲル]
1962年生まれ、北海道苫小牧市出身。東京大学卒業後、旧自治省を経て2001年から新潟大学法学部助教授。2007年から教授、法学部長などを歴任。専門は行政学、地方自治、公共政策、食によるまちづくり。2015年から群馬県みなかみ町参与、2017年から(一社)日本食文化観光推進機構理事長を兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。