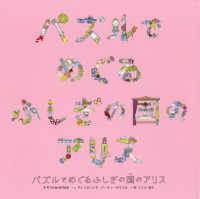内容説明
水分をせっせと取ることは、現在の日本人の生活習慣には悪いことばかりで、良いことはまずありません。水分補給とサラサラ血液は関係がない!冷房が効いた室内の水分補給は危険!塩分の多い、少ないは血圧と無関係!
目次
1章 現代の日本人の体は水浸し―水で血液はサラサラにならない(人間の体とは;「病」とは熱がこもること ほか)
2章 海外の気候と日本の気候―水分補給の必要量が違う外国人と日本人(「水毒」をチェックする方法;西洋医学と東洋医学はここが違う ほか)
3章 水分の過剰摂取が招く病気―水と熱の代謝で紐解く体調不良の原因(膀胱炎;花粉症 ほか)
4章 体から余分な水を追い出す漢方薬―生薬の成り立ちから見る効果・効能(漢方の効果;桂枝(ケイシ) ほか)
著者等紹介
笠井良純[カサイヨシズミ]
1959年生まれ。東京薬科大学大学院博士課程前期修士課程修了。薬学修士。渋谷区で大正10年から続く薬局・有限会社笹塚薬局の三代目。大学院修了後、日水製薬株式会社中央研究所勤務を経て実家を継ぐために漢方の勉強を始める。なぜその植物が生薬として使われるようになったのか、を紐解く独自の「生体生薬学」を創設。体の熱代謝と水分と病気の関係を研究し、「体の過剰な水分が冷えの元となって熱が内攻してすべての病気を引き起こす」という理論によって、相談に訪れる患者のさまざまな病気に対し、独自の漢方処方で症状を改善させている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
M.O.
山のトンネル
ココアにんにく
Humbaba
Humbaba
-

- 電子書籍
- 横浜ラブ・コネクション【分冊版】 2 …
-

- 電子書籍
- はたらく魔王さま!ハイスクール!1 電…