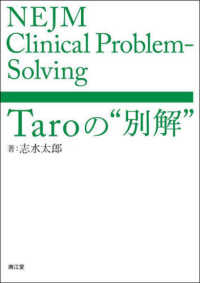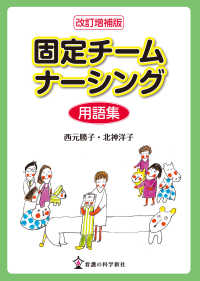内容説明
精神の危機を「エロイ・エロイ・ラマ・サバクタニ」で乗り越え、ギャラリー白い点を拠点に未踏の冒険に踏み出す。副島種臣、河東碧梧桐の衝撃を世に知らしめ、新しい書史を確立。現代芸術の世界を毅然と歩んできた書家は何を感じ、考えてきたのか?
目次
第1章 書との出会い
第2章 人生の冒険 時代を書く
第3章 古典への回帰とタブーへの挑戦
第4章 古典への退却
第5章 ふたたび、時代を書く
第6章 劣化する日本語のなかで
著者等紹介
石川九楊[イシカワキュウヨウ]
書家。京都精華大学客員教授。1945年、福井県生まれ。京都大学法学部卒業。1990年『書の終焉 近代書史論』(同朋舎出版)でサントリー学芸賞、2004年『日本書史』(名古屋大学出版会)で毎日出版文化賞、同年日本文化デザイン賞、2009年『近代書史』で大佛次郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読書家さん#2EIzez
3
大事なことを書き忘れたが、この人の書を読み解くのは ナゾナゾに似ていて本人のみが知りうる面が多そうだ、 なぜか理解できそうにないとわかってしまった。 それが人の道ってことにもなるけど。 とにかく書の芸術、日本語や文章のお手本のような人だ こんな人がまだいるとは、、 長生きしていただきたいなー。2025/01/27
読書家さん#2EIzez
3
また日本語についての本としても、これ一冊あれば充分すぎるくらいよいことが書いてある 個人的には時代をかいた章9.11のエンパイアステートビルの事故以後の解説していた部分やカラマーゾフの兄弟と罪と罰、そして東京都庁をデジャブとしている思考も似ていてよかった。 時代の振り返りとしても読んでいて爽快だし、例にあげれば揺さぶられ余計なものがおちる地震が割と好きだと言うトコなど、社会批判も共感できたし学びもあった怖いのは原発や地震そのものではなく、それらの人の反応や津波だそうだ。 2025/01/27
読書家さん#2EIzez
3
石川九楊さんの自伝とあるが、時代をテーマにした書と解説、歎異抄の書そして源氏物語、徒然草、方丈記などの古典作品をテーマに20年かけて解釈をして墨という書で表現している。書は縦に伸びていくのが基本だということで独自の群れない人生もはじめに影響をうけた詩、下へ下へ根元の花のない部分と個人的に重なった印象をうけた。 良寛の書が本当の意味で出会った書とあった。間という時間と空間をみごとに惜しむようゆっくり広く描いているとある。千年前でも筆遣いをなぞれば書いている人が蘇ってくるそうだ。こういう表現は書の他にないそう2025/01/27
林克也
2
戦慄と同意。その書と思想に。 この夏、名古屋での展覧会を見逃してしまった。しかし、この本を読む前に見るのと、今、この本を読んだ後で見るのとでは全く違う経験になると強く思った。つまり、夏に展覧会を見なくてよかった、ということ。 これから、石川九楊氏の作品を生で見ると、戦慄を覚え、畏れおののき(この“畏れ”)、わなわなと泣き出してしまうかもしれない。 フクイチの吉田所長への不可解な英雄視の話、成る程そうだなっていうことと、タテ書の封筒にヨコ書きで宛名を書いてくる人がいること、これは参ったなぁって思った。 2019/10/23
-

- 洋書
- Soluções …