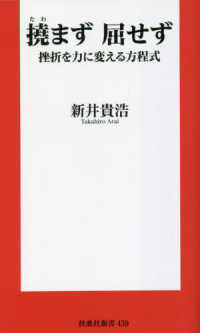内容説明
省略されて変身した日本語、よくよく見るとおかしな英語。言葉の狭間を自在に行き来する、片仮名語。作家・片岡義男は、今日も言葉に驚いている。エッセイ88編。
目次
バッテンボーからビル・ライス・テレビの国へ
Zicoとジーコはおなじなのか
ミーティングでペンディングとなる
すべてが片仮名語になった国とは
千差万別という面倒くささをいっきに解決するには
のっける気持ちはことのほか大きい
思い出は言葉をめぐって
「珈琲」のひと言ですべてが通じた時代
いまでは聞かないし見ない言葉
男性とは明確に区別された生き物がいる国〔ほか〕
著者等紹介
片岡義男[カタオカヨシオ]
1939年東京生まれ。早稲田大学在学中にコラムの執筆や翻訳を始める。74年「白い波の荒野へ」で小説家としてデビュー。翌年発表した「スローなブギにしてくれ」で野性時代新人賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
32
繊細/センシティブさに触れた思いがする。世に氾濫する(そして、かなりの程度「この私」もその「氾濫」に加担しているはずの)言葉について片岡義男は歯に衣着せぬ率直さを以て語り尽くす。しかし彼は誰の威を借りるわけでもなく彼個人の皮膚感覚や身体感覚、そして記憶をベースに分析/解析と考察を連ねる。その徒手空拳な有り様が「いかにも片岡義男らしいな」と思った。徒党を組むことなく世界の片隅で個人の立場から物申す。その姿勢を見習いたいとも思う。それにしても片岡義男は何と若々しい感受性を備えた書き手なのだろう。実にフレッシュ2023/02/18
踊る猫
27
世に日本語を論じた本はゴマンとあり、いくつかは確かに傑作である。だが片岡義男のアプローチはそうした本とはやや異なり、「片岡義男を通した日本語」つまり「自分というプリズムから放たれた日本語」を論じているのではないか。これはむろんそのプリズムを信頼していなくてはできないことだ。片岡は日本文学の(隠れた?)重鎮かつ大ベテランとしてプリズムからユニークな光を放つ。私自身日本語を母国語として育ちなおかつ英語の魅力に魅せられている者として、彼のセンスの鋭利さには感服するしかない。スノビズムとは無縁の愚直さに敬意を抱く2022/07/29
踊る猫
21
私的な事情を明かすと、ひょんなことから英語で日記を書き始めた。そのせいもあって、片岡義男がまさにそんな「バイリンガル」作家の先陣を切る存在であることに唸らされる。しかも、このエッセイ集を読む限りでは彼はまだまだ現役で、ともすると無目的に発展し続けるカオスである日本語のその変化ぶりを見続け、違和感を言葉にし続けるという作業を続けているみたいなのだ。80歳を過ぎ、ここまでフレッシュな感受性を持ち続けられていることは驚くべきだろう。彼は今一体なにを見つめ、どう考え続けているのか。彼はまさしく1個の「知性」と思う2021/10/07
食物繊維
3
翻訳の仕事経験もある片岡義男さんの日本語に関するエッセイ。面白かったです。カタカナを使ったら外来語もかなり日本語化するという指摘に考えさせられたり。私はレジ係の人のマニュアル通りの会話は変だとあまり感じなかったのですが、海外在住の方の体験談や片岡さんの考察を読むとある意味、かなり崩れたというか変化した言葉の使い方なのだなと気付かされます。勉強になる本です。日本語や日本に対しての諦念が微かに漂っている気がします。2024/08/03
horuso
3
言葉についての深い考察を期待して手に取ったが、日本語に関するもっと気楽で楽しい読み物だった。「半ライスという言葉を初めて知ったときの深い感銘」に共感できる人なら楽しめると思う。雑誌の連載をまとめた本だが、実際、自分でもそのトピックについて思い出したり考えたりしながら読むのに向いた内容だから、一気読みせず、雑誌で読むように少しずつ読めばよかった。それにしても、片岡義男は子供の頃から言葉への感受性が極めて高い人だったんだなあ。作家はみんなそうだというわけでもないだろう。いつも思うことだが、彼の文体が大好きだ。2021/12/19