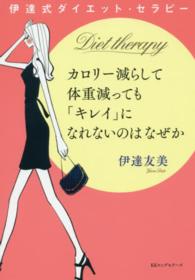内容説明
人類史から哲学をたちあげる。近代の自律/他律を超える「異律」の原理から、自然/人間の二元論を問い直し、来るべき社会性をめざす。
目次
第1章 社会性の自然化
第2章 異律
第3章 人間社会の異律的組織化の微分要素
第4章 人間社会の歴史―人間の相互行為のパターンの組織化と学問の起源
第5章 現在とは何か―近代制の構造分析、資本主義、法、自然法則
終章 内在の形而上学
著者等紹介
近藤和敬[コンドウカズノリ]
1979年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
1
哲学、社会、価値:学問と価値 現代の価値の布置 社会性の自然化 異律 人間社会の異律的組織化の微分要素 人間社会の歴史―人間の相互行為のパターンの組織化と学問の起源 現在とは何か―近代制の構造分析、資本主義、法、自然法則 内在の形而上学: 強度の絶対零度 セリー化ー必然性 セリーと反復 差異のフラクタル・スケールとしての共通のもの 認識の基礎 強度的な場と構造の接続 条件的なものの認識とかつての自然科学 治療的理解 構造変換と条件的なもの 構造のカタストロフか多構造を培養するインフラ構造か2024/02/07