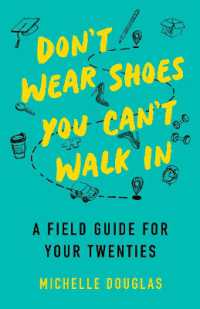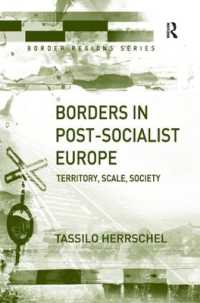内容説明
差別や偏見に繋がりかねないリスク要因を数え上げ、子どもを家庭から引き離す政策を維持するのか。社会保障や福祉サービスを整備し、家族に貼り付けられた「虐待リスク」を社会の責任で確実に減らしていくのか。私たちはどちらのタイプの社会を選ぶべきか。
目次
第1章 児童虐待の発見方法の変化―目視からレントゲン、そしてリスクへ
第2章 心理と保険数理のハイブリッド統治
第3章 「子育て標準家族」はどこから来たのか
第4章 ネオリベラルな福祉
第5章 親による親子分離の語り
第6章 一時保護を経験した子どもの語り
第7章 多文化と児童虐待
第8章 「不十分な親」の構築―ヤングケアラー概念の批判的検討
第9章 ソーシャルハーム・アプローチの挑戦
著者等紹介
上野加代子[ウエノカヨコ]
大阪市立大学大学院生活科学研究科生活福祉学専攻後期博士課程単位取得退学。大阪府立大学大学院人間文化学研究科・博士(学術)。現在、東京女子大学現代教養学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
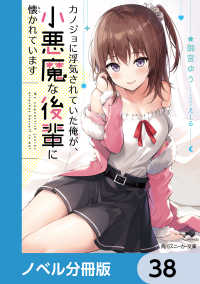
- 電子書籍
- カノジョに浮気されていた俺が、小悪魔な…