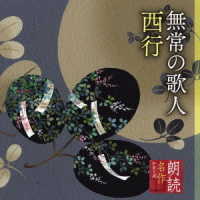内容説明
多様にあるケアの経験を、当事者だった7人が書き下ろした、それぞれの「わたしのストーリー」。
目次
第1章 誰のせいでもないし、誰も悪くない
第2章 ノートの片隅から
第3章 障がいのある妹と私―「きょうだい」として感じてきたこと
第4章 ケアをめぐる価値観の違い
第5章 耳の聞こえない両親と聞こえる私
第6章 矛盾を抱きしめて生きるということ
第7章 母と過ごした時間について
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
224
難病の母をケアしてきた子供は大変な重荷を背負ってきたともいえるが、彼は真面目な普通の若者で、進学や就職といった岐路で常に介護のことを考え、家族と連携してきた。他の人にはない経験を強みと考えるまでになったそうだ。一方通行ではなく、母から大切なものを受け取ったと語っている。本書はヤングケアラーたちの揺れる思いが率直に綴られており、中でも十代後半から社会に出て働く時期にかけての周囲との「溝」については、細かい記述から色々知れてよかった。可哀想な子供という見方ではなく、彼らの立場から介護の意味を真摯に問うている。2022/02/09
ごへいもち
35
あまりの健気さに心が痛み過ぎて読みやすいのに読了に時間がかかった。幼い時から介護が生活の中心。自宅での時間の全て、寝ている時もお母さんは生きているか心配で息を確かめに行く。我慢が習性になってしまって自分の希望、気持ちがわからない、「思ったことを言ってみて」と言われても言えない。聴覚障害の両親は手話を禁じられて生きてきたので親子の会話も用件だけ、人とのコミュニケーションの取り方を教えてもらっていないためお店で注文をするのもタイミングや声の大きさ等全てわからない…等、書ききれない。今年のベスト10入り2022/02/17
zel
24
当事者たちのストーリー。文字の裏側にある状況や思い、葛藤などを感じながら読み進める。答えのない答えを求めて思いを巡らせるけれど、やはり答えはない。それぞれのストーリーがあって、思いがあって。それを聴くこと。それが大事なのかなと。アウトプットする段階に至っていない方もたくさんいるだろう、矛盾を抱えてみえる方もたくさんいるのだろう。2021/11/23
ずっか
21
第三者の取材や視点ではなく、ヤングケアラーだった本人達による手記。文章を書くことを生業としている人ではないのですが、分かりやすい文章で、様々な状況(親の病、家族の障害、祖母の介護など)や本人の心の状態などを知ることができました。オススメです。2021/11/14
ドシル
19
ヤングケアラーと一言で言ってもさまざまな形がある。 研究者である渋谷智子氏が、色々なヤングケアラー体験者に依頼して個々の経験や視点を執筆してもらいまとめた一冊になっている。 コーダやきょうだい児と同じように、ヤングケアラーの方々も自分がおかれた状態に名称があるとは思っていなかったという話が多く見られた。 ヤングケアラーが身近にいたらどう声をかければ良いのか、正解はないのだろうと思う。 正解はないけど、理解する努力をしたいことは伝えたいと思う。2021/02/03
-

- DVD
- 拳精 デジタル・リマスター版