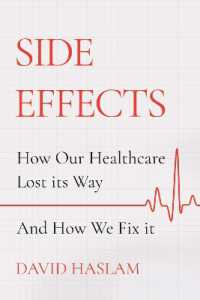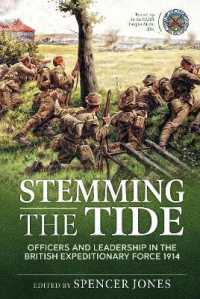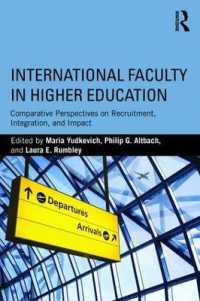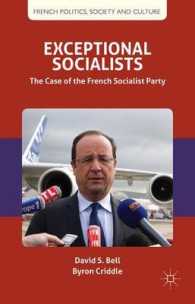出版社内容情報
古代女王の鬼道に見る、女神アマテラスを祀る天皇制の始原と、神話と正史の結節点を探り現代につなぐ日本通史。古代女王の鬼道に見る、女神アマテラスを祀る天皇制の始原。
二十世紀の現人神の「神聖」に通底する、三世紀の巫女王の「呪性」。
記紀と倭伝の齟齬を衝き、「神話」と「正史」の結節点を探る、日本人および日本国起源の再考。
天孫降臨から昭和の敗戦を貫き、そして現在の「象徴」を見据えた通史。
序章
第1章 アマテラスと卑弥呼
女神オオヒルメ 一書曰 水稲耕作という革命 青銅鏡の役目 銅鐸に映じる異神 カミの交代 ワとヤマト 朝鮮半島南部への進出 持衰 易姓革命と共立 アマテル 公孫淵と司馬懿 ポスト卑弥呼
第2章 空白の四世紀
奈良盆地の古墳群 ヤマトトトビモモソヒメと三輪山 景初四年銘鏡 七支刀の銘 編纂者の作為 広開土王碑と神功皇后紀 祖国という死語
第3章 女王国の現実
景初二年と三年 倭国の人口 陣頭巫女の系譜 神功皇后の新羅征伐と出産 応神という胎中天皇 生口の価値 朱いイケニエ
第4章 卑弥呼以死
『三国志』の注記
狗奴国の不満と魏の思惑 王殺し 二つの「建国」 三王朝交代説
第5章 倭の五王
武と雄略とワカタケル 大悪天皇 継体の出自と皇統の分立
第6章 蘇我氏と飛鳥王朝
タリシヒコとは誰か 日出ずる処の天子 日本という国号 律令の黎明
第7章 中大兄皇子
蘇我氏と渡来人の関係 鎌足の初出 俳優起用のアイディア 改新之詔
第8章 白村江の戦い
斉明女帝の呪性 近親婚というタブー 昭和天皇の「長い記憶」 天智暗殺疑惑と額田王の挽歌
第9章 壬申の乱
敗戦以前の歴史教育 天武天皇という異能の術者 赤という色 別の血筋がもたらした姉弟の悲劇
第10章 神話と歴史
事実化された「詩」 津田左右吉の以前以後 「天壌無窮」の神勅 水穂国のイネ 『くにのあゆみ』 漢文と和習が混在する「正史」 持統女帝と藤原不比等
第11章 伊勢神宮と天皇家
伊勢と三輪山の荒魂 アマテラス信仰の源流 心御柱の以前 アマテラスと女性性 「何処に人の代ならぬ神の代を置くことができようぞ」 浮いた軍事費 不改常典と平城京 出雲の賀詞と伊勢の禁令
第12章 神から仏へ
仏教立国に向かった天皇の熱情 末法という岐路 祭祀権の所有者として
の源氏 元寇とその戦後 「御謀叛」と「悪党」 集合的無意識 流離う神の国 天皇をめぐる江戸期の視点と『大日本史』 本居宣長と賀茂真淵 新たな大和魂の誕生
第13章 仏から再び神へ
島崎藤村の『夜明け前』とコミュニスト尾崎秀實 揺らいだ国体
第14章 神から人間へ
神聖死 三島由紀夫が告発した「虚無」
終章
あとがき
篠田正浩[シノダマサヒロ]
著・文・その他
内容説明
その鬼道に見る、女神アマテラスを祀る天皇制の始原。二十世紀の現人神の「神聖」に通底する、三世紀の巫女王の「呪性」。記紀と倭伝の齟齬を衝き、「神話」と「正史」の結節点を探る、天孫降臨から昭和の敗戦を貫き、そして現在の「象徴」を見据えた通史。書き下ろし。
目次
アマテラスと卑弥呼
空白の四世紀
女王国の現実
卑弥呼以死
倭の五王
蘇我氏と飛鳥王朝
中大兄皇子
白村江の戦い
壬申の乱
神話と歴史〔ほか〕
著者等紹介
篠田正浩[シノダマサヒロ]
昭和6年(1931)、岐阜県生まれ。24年、早稲田大学第一文学部入学、中世・近世演劇を専攻。25年、箱根駅伝出場、二区を走る。28年、早大卒業、松竹撮影所入社。35年、『恋の片道切符』で映画監督となり、大島渚、吉田喜重らとともに「松竹ヌーベルバーグ」と称される。41年、松竹退社、翌年、独立プロダクション表現社を妻岩下志麻と設立。61年、『鑓の権三』で第三十六回ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞(1986)。平成15年(2003)、『スパイ・ゾルゲ』で監督引退。22年、日本の芸能史を再構築した著書『河原者ノススメ死穢と修羅の記憶』で第38回泉鏡花文学賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
らむだ
hasegawa noboru
-
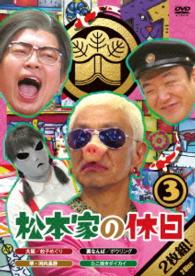
- DVD
- 松本家の休日 3