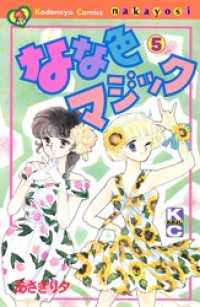目次
第1話 ルシアとごみの山(グアテマラ)―飢餓問題(ルシアの国グアテマラ;世界では多くの人が飢えている;子どもたちは選べない ほか)
第2話 ティンボロの水くみ(シエラレオネ)―水問題(ティンボロの国シエラレオネ;よごれた水で命を失う子どもたち;不衛生な状態が、貧しい人びとをさらに苦しめる ほか)
第3話 学校に通えるようになったワタナ(カンボジア)―貧困と教育(ワタナの国カンボジア;先進国にも責任はある;借金に苦しむ途上国 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マカロニ マカロン
6
個人の感想です:A-。表紙の写真はわずかなスープを4人で分け合っているアフガニスタンの子供たちです。マルサスが『人口論』のなかで人口増加が食料の増加を上回り、飢えは人口を自然淘汰するものだと言っていますが、食料を人類で平等に分配すれば、1人あたり年間360kgの穀物を得られるとのこと。難民が援助物資の小麦粉を煮炊きするため避難キャンプ周辺の野山の木を伐り、はげ山にしてしまい周辺住民からの恨みを買うなど、考えさせられる問題が多い。食料、水、教育における子供の貧困問題が分かりやすく挿絵付きで語られています。2015/03/07
とよぽん
2
日本で「貧困ビジネス」なるものが存在(横行)する一方で、海外の貧しい国に対する「援助」が、結果的に当該国の教育を後回しにさせている。成人の識字率が50%以下の国は、世界に10カ国あり(総務省「世界の統計」2012年)、全てアフリカ中西部の国々である。富の偏在を、どうすれば解消できるのだろうか。2015/05/06
ruri
1
食べ物があること、水があること、教育の重要性を認識してること。2016/08/19
あろぴ
0
現実を知る事から始める教育が必要だが、「どこ吹く風状態」でしか受け止めないのも現実。豊かな国の中で「貧困」を自分を置き換えて考えるのは難しい、それが悔しくもある。育った国や環境で「当然」が違ってくる。「人間の人間としての平等」とは何だろうと考えさせられる。どうしていいのかわからない自分がもどかしい。2015/08/16
genta
0
図書館の特設コーナーで目にして手に取りました。直接的な解決方法を考えるのは難しいけど、関心を持つことが大事なのかなと思います。私も「飢餓」のない世界に貢献できる生き方をしていきたいです。まずは日々の食事に感謝して子どもと一緒に全力で「いただきます」をします!2022/06/21