目次
食べものつくる建築土木(丸干し大根の大根櫓(宮崎県宮崎市田野町)
柿屋(京都府綴喜郡宇治田原町) ほか)
土地の特性を活かすちえのかたち(木造ビニールハウス(愛媛県伊方町)
遠州灘の砂防(静岡県掛川市) ほか)
山・里の美味しい食べもの(串柿の柿屋(和歌山県伊都郡かつらぎ町)
凍み豆腐干し(福島県福島市) ほか)
くらしを守り、くらしを彩る(ナヤ、スベリ(愛媛県伊方町)
壁結(福岡県うきは市))
海・川のめぐみをうけとるしかけ(海苔ヒビ(三重県南伊勢町)
カキ養殖(台湾金門島) ほか)
著者等紹介
後藤治[ゴトウオサム]
1960年東京都生まれ。工学院大学建築学部教授。文化庁文化財保護部建造物課文化財調査官であった経験から歴史的な建築物や町並の保存・活用に力を注ぐ
二村悟[ニムラサトル]
1972年静岡県生まれ。工学院大学建築学部客員研究員、ICSカレッジオブアーツ非常勤講師ほか
小野吉彦[オノヨシヒコ]
1967年愛媛県生まれ。写真家。(公社)日本写真家協会会員。文化財建造物撮影を中心に活動(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
36
読み友さんの感想を読んで。おお、こういう食にちなんで作る建物のことを「建築土木」っていうんだ!そっか、土台を作るからかあ…。子どものころ千葉でよく見た、落花生を干すために積み上げられたあれ、あれは土木に入らないんですね。どの写真も美しくてうっとり眺めました。こういうの他のアジア諸国のものと比較してみたい…。宇治の抹茶づくりのための覆下、素敵です。私がう時に行った時見たものはもっとビニールとかの覆いだった気がするので、こういう伝統的なものを見てみたいです。2025/05/16
アナクマ
29
農山漁村の風景にとけこむ/目をひく特別な建築物。大根やぐら、ウド小屋、凍み豆腐干し。スガキや粗朶や藁の防風垣に、天草干し。〈建築家なしの建築/プライマリー・ストラクチャー〉と形容される「ありあわせの材料で専門家でない人たちが明快な目的のもとに作る」建築・土木。「地形の特殊性。素材が限られる。私たちが感じ取る魅力に対して作り手の意識が向けられておらず功名心がなく匿名的である(それはどうかな?)」それらの記録。必然性が生む造形に魅力を認められる目を保ちたい。人手が加えられたそこらへんの何かは、何であれ面白い。2025/01/22
魚京童!
19
昔ながらの手法はこうでね、最新はこんなのもあるよっていう話なら面白いのだろうが、昔からこのやり方を守っています。伝統です。正統です。あなたのやることは異端です。みたいなことを言われましても困ります。2024/07/17
menmen
11
ドライブしていると、何を作っている建物なんだろう?と、田畑の周りにある建造物に目が行きます。この本は、そんな私の疑問に写真つきで親切に教えてくれているような本です。まだ見たこともない、または地域差のある櫓だったり、たとえば養殖の様子だったり、そんなものを探しに、この本を持って出かけたくなりました。マニアックかな?(笑)2014/02/13
たらこりっぷ
9
人間はしかけを準備し、自然の力や自然の恵みを上手に選び出してたべものに詰め込んでいく。大根を干すやぐらに干し柿の暖簾。人間はいつもたくましく、いかに食を確保するかに一生懸命です。この本にある写真には人間の姿がほとんど写っていませんが、しかけそのものを見るに付け、人間の偉大な力を感じずにはいられません。ほれぼれ~とします。見に行って美味しいたべものを味わいたいです。2014/03/11


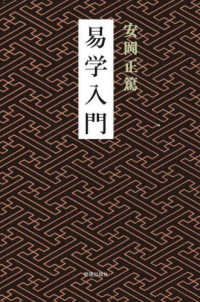
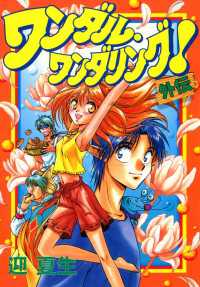
![めしばな刑事タチバナ(40)[たこ焼き・オン・マイ・マインド] TOKUMA COMICS](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0940671.jpg)




