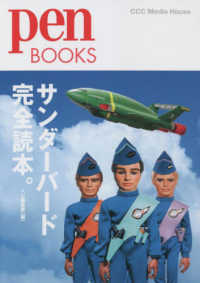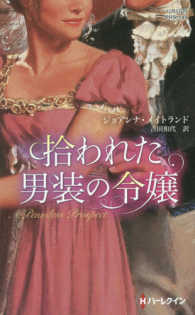内容説明
なぜワークショップをやるのか?どうしてアートなの?ファシリテータに求められる能力とは?さまざまな疑問に教育学の視点から答え、新たな美術教育の可能性を提示する。
目次
はじめに この本のためのガイドツアーとして
第1章 教育からみた造形ワークショップ
第2章 企画力―プランニングの立脚点
第3章 組織力―プレゼンテーションとコミュニケーション
第4章 記録力―記録と表現のプロセスとして
第5章 これからの造形ワークショップにむけた質疑応答
資料編 造形ファシリテーション能力獲得プログラムなどの概要
著者等紹介
高橋陽一[タカハシヨウイチ]
1963年生まれ。武蔵野美術大学造形学部教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程満期退学。日本教育史(国学・宗教教育)を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
そうとめ
0
ワークショップという言葉の定義が書かれている。美大の先生が書かれているが、とても言語を大切にしている姿勢が貫かれているのは、今まで読んできたワークショップの本とは違うなと感じなした。 以下、まとめ: 「ワークショップとしか言えないワークショップ」の定義 ... 参加者が主体となった教育であり、その過程や結果を参加者が享受することを目的とするが、その知識や技術の習得や資格の取得などを目的とせず、さらに準備して見守るファシリテータは存在しても、指導して評価する教師が存在しないもの」 中野民夫「ワークショッ2012/04/19