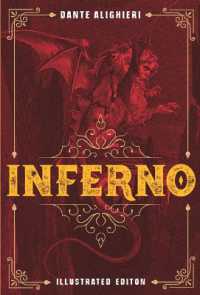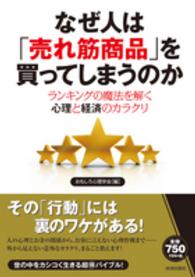出版社内容情報
土偶・土器・住居址などから縄文時代中期の関東・中部地方の環状集落遺跡の実態に迫る。集落から縄文社会を探る
縄文時代中期の関東・中部地方の環状集落とよばれる集落遺跡の実態を探る目的で、新地平グループと呼ばれる研究者を中心に数次にわたる研究会を重ねてきた。その成果をもとに、論をまとめたのが本書である。
土井義夫、石井寛からの研究史を踏まえた提言を受け、黒尾和久が集落群研究の時期区分を問いただし、小林謙一が静的な理解であった環状集落を環状化集落として捉え直す。山本典幸が小林のフェイズ設定へ批判を加えつつ景観論へと止揚を試みる。異なる視点として、櫛原功一が住居型式から、今福利恵が土器型討論から、塚本師也が貯蔵穴から、中山真治が土偶の廃棄から、五十嵐彰が第2考古学的に環状集落を検討する。環状集落論の解体と再構築を提言する本書は、縄文研究の新たな地平を目指す一歩となろう。
小林謙一 序 縄文の地平研究の歩み
―縄文研究の新地平から地平へ―
土井義夫 縄文集落研究と集落全体図
―分析に使える基礎資料はどれだけあるのか―
石井 寛 遺跡群研究の現状
黒尾和久 「横切りの集落研究」から「横切りの遺跡群研究」へ
―平均住居数という考え方がもたらすもの―
小林謙一 集落の環状化形成と時間
山本典幸 縄文集落と景観の考古学
― 一時的集落景観論のアポリア―
五十嵐彰 〈場〉と〈もの〉の考古時間
―第2考古学的集落論―
櫛原功一 住居型式と集落形成
塚本師也 貯蔵穴の増加と集落の形成
―縄文時代中期前葉の関東地方北東部の状況―
今福利恵 土器系統からみた縄文集落
―多摩ニュータウンNo.446遺跡の分析―
中山真治 土偶と出土状態
―多摩地域の縄文中期前半の土偶多量出土遺跡の検討―
小林謙一 まとめ 縄文の地平を越えて
―集落および竪穴住居跡から縄文社会をさぐるために―
小林謙一 黒尾和久 中山真治 山本典幸[コバヤシケンイチ クロオカズヒサ ナカヤマシンジ ヤマモトノリユキ]
小林謙一:中央大学文学部教授。主要著書・論文に『縄紋社会研究の新視点―炭素14年代測定の利用―』(六一書房・2004)、「弥生移行期における土器使用状況からみた生業」『国立歴史民俗博物館研究報告』(2014)がある。
黒尾和久:国立ハンセン病資料館学芸部長。主要著書・論文に「集落の分析法? 集落遺跡の形成過程 「環状集落跡」の形成プロセス」『縄文時代の考古学』第8巻(同成社・2009)、『東アジア教育文化学会企画 靖国・遊就館フィールドワーク 靖国神社と歴史教育』(共編著、明石書店・2013)がある。
中山真治:府中市役所。主要論文に「勝坂式土器の型式と地域―西関東中部地方の縄文時代中期中葉を中心に」『地域と文化の考古学1』(六一書房・2005)がある。
山本典幸:早稲田大学文学学術院講師。主要著書・論文に『現代考古学事典』(共著、同成社・2004年)、「縄文時代中期終末から後期初頭の柄鏡形敷石住居址のライフサイクル」『古代』第138号(2016)がある。
目次
序 縄文の地平研究の歩み―縄文研究の新地平から地平へ
縄文集落研究と集落全体図―分析に使える基礎資料はどれだけあるのか
遺跡群研究の現状
「横切りの集落研究」から「横切りの遺跡群研究」へ―平均住居数という考え方がもたらすもの
集落の環状化形成と時間
縄文集落と景観の考古学―一時的集落景観論のアポリア
“場”と“もの”の考古時間―第2考古学的集落論
住居型式と集落形成
貯蔵穴の増加と集落の形成―縄文時代中期前葉の関東地方北東部の状況
土器系統からみた縄文集落―多摩ニュータウンNo.446遺跡の分析
土偶と出土状態―多摩地域の縄文中期前半の土偶多量出土遺跡の検討
まとめ 縄文の地平を越えて―集落および竪穴住居跡から縄文社会を読み解くために
著者等紹介
小林謙一[コバヤシケンイチ]
中央大学文学部教授。1960年神奈川県生まれ。総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻博士後期課程修了(博士、文学)
黒尾和久[クロオカズヒサ]
国立ハンセン病資料館学芸部長。1961年東京都生まれ。東洋大学大学院文学研究科国史学専修修士課程修了
中山真治[ナカヤマシンジ]
府中市役所。1960年東京都生まれ。明治大学文学部史学地理学科卒業
山本典幸[ヤマモトノリユキ]
早稲田大学文学学術院講師。1963年山口県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程修了(博士、歴史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 洋書
- Aaron's Rod