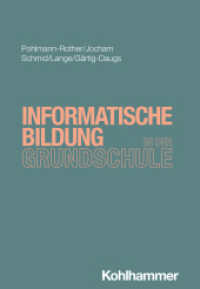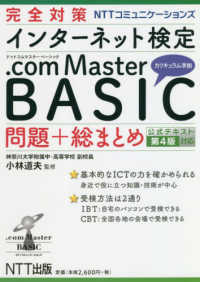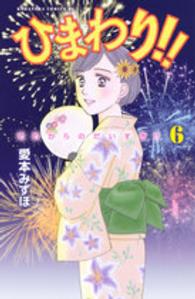出版社内容情報
図書館の前身とも言える江戸時代までと、明治時代以後、近代的な図書館ができてから現在までを、多くの図版や絵で見ながら、日本の図書館の変化と本来の姿を追っていく。
図書館は、いつ、だれが、なんのためにつくったのだろう。文字が生まれ、記録されたものを保管する場所ができ、遣隋使船が本を海の向こうから運んできた。貴族や武士や大名は施設図書館をつくり、学校附属の文庫もできる。近代的な図書館は欧米に学んで明治時代にできるが、戦争で多くの図書館や本が焼けてしまう。戦後、各地に中小の図書館がつくられ、市民たちは利用し、支え、広めていく。震災下でも図書館は重要な役割を果たす。巻頭に年表、巻末に索引付。
内容説明
古代から現代まで、多くの図版や絵で読み解く、初めての日本の図書館の歴史。だれが、いつ図書館をつくったの?図書館は時代によって変わってきた?戦争や災害時の図書館は?学校に図書館ができたのはいつ?私の町の図書館の歴史は?年表とさくいんで調べられる!
目次
文字の誕生と記録
紙の発明と本の形
本が海をわたってきた 飛鳥・奈良時代
たくさんの本を収めた場所 奈良・平安時代
写経所は昔の図書館? 奈良・平安時代
貴族の文庫と女性作家の登場 平安時代
武士のつくった文庫と学校 鎌倉・室町時代
大名・貴族の文庫と町の本屋 室町~江戸時代
江戸幕府の出版事業 江戸時代
武士も町民も本を読む 江戸時代
子どもも農民も本を読む 江戸時代
近代図書館のはじまり 明治時代
各地に図書館が誕生 明治時代
“図書館の父”佐野友三郎 明治時代
図書館の発達と国の教育 明治・大正時代
図書館のサービスと大震災 大正時代
戦時下の図書館 大正・昭和時代
占領下につくられた図書館 昭和時代
法律の制定と読書運動のはじまり 昭和時代
子どもたちに読書の場を 昭和時代〔ほか〕
著者等紹介
奥泉和久[オクイズミカズヒサ]
1950年、東京都生まれ。日本図書館協会、日本図書館文化史研究会、日本図書館研究会、としょかん文庫・友の会などの会員
堀切リエ[ホリキリリエ]
1959年、千葉県市川市生まれ。著書に『伝記を読もう 田中正造』『同 阿波根昌鴻』(あかね書房)、『非暴力の人物伝 ガンジー・阿波根昌鴻』(大月書店)など
いしいつとむ[イシイツトム]
1962年、千葉県香取市生まれ。絵本に『子どもたちの日本史(全5巻)』(大月書店)、『ふねのとしょかん』(文研出版)、『くるしま童話名作選 なだれうさぎ』『日本の伝説 きつねの童子 安倍晴明伝』(子どもの未来社)などがある。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
明るい表通りで🎶
shiho♪
紀梨香
奏
かはほり
-

- 和書
- 「設景」その発想と展開