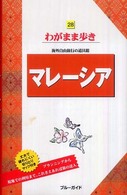内容説明
織田信長は日本の統治形態を変え、戦国時代と中世を終わらせた。画期的な経済政策は豊臣秀吉に受け継がれ、明の貨幣制度および国際貿易体制の大変化に日本はようやく追いつく。秀吉は天下統一の勢いのまま征明を目指すが、そこには大きな落とし穴が待っていた。
目次
序に代えて―「悪貨」が「良貨」を駆逐する
第1部 織田信長と貨幣制度(信長の本当の業績;信長の経済政策;信長vs.義昭の裏で進行していた貨幣制度の大転換)
第2部 豊臣秀吉の国内政策(国際情勢を理解していた秀吉の改革;牙をぬかれた寺社勢力)
第3部 豊臣秀吉の対外政策(キリスト教国の脅威;「朝鮮出兵」失敗の本質)
結びに代えて―過去の失敗に学び、未来に生かす経済学的思考
著者等紹介
上念司[ジョウネンツカサ]
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
52
経済法則という視点から見ることでこの時代も見通しが良くなります。今でも過大評価されることが多い信長ですが、見地や楽市楽座・撰銭令などは不十分な結果に終わったとされています。日本は鉱山の発見や精製技術の発達により、銀の生産が拡大し、明の経済が銀を通貨にするように変えていきます。秀吉の朝鮮出兵についても、秀吉の気まぐれから起きたとする説ではなく、秀吉が世界情勢を理解していたことから起こしたことがわかります。ただし、手段についてはランドパワーの観点で行動したため、十分な成果を上げることができなかったようです。2019/10/30
saga
41
本シリーズ3冊目。織豊時代は著者も力が入ったのか、歴史の「もしも」に触れる記述が多かった。大陸の先進技術、輸入品などで財力をました宗教勢力が、自衛のための戦力を保持する経緯もよくわかった。そして、宗派を優先させて国家を考えない勢力から、信長から秀吉にかけてその権力を削いでいく動きも納得できる。海外からの銭貨に頼ったのは、日本に銅を精製する技術が乏しかったためで、経済の原則からデフレとなり、それが米本位制につながっていく。もし、信長が暗殺されずに、金銭を主体とした経済が発達していたとしたら……?!2019/07/22
ころこ
34
資本の取替可能性に焦点を当てれば、信長の行った武将の配置換えや検地は近代への重要な段階を進んだことになります。同時代に、岩見銀山の発見と銀貨の鋳造が、前時代のデフレから一転してインフレ基調となり経済成長を促します。信長は、自らも本拠地を6回移転し、その度に、城と城下町をつくり道路を整備して関所を廃止しています。他方で、組織再編が仇となり、リストラ恐怖の光秀に裏切られたとしています。天下統一の唯物的な要因として経済をみるのか、インフラ整備の障害として敵と戦をしたとみるのか、新たな視点で歴史と経済を論じます。2020/01/26
Syo
26
こういうのはいいねぇ。2022/01/20
ゆきこ
25
ゼロからイチを生み出す「創業者タイプ」の信長、信長の政策を着々と推し進める「経営者タイプ」の秀吉、という観点がおもしろかったです。これまでの常識であった中世的な社会秩序を破壊していく信長は本当にすごい人物だったと改めて感じました。それにしても、秀吉の晩年は残念でならないです。歴史を学び、秀吉の失敗をきちんと今に生かさないといけませんね。2020/09/16