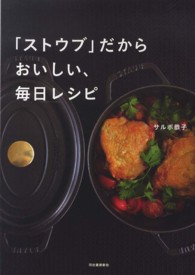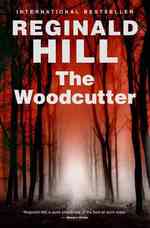内容説明
メディアの協働・モードの交錯。映画はいつの時代も文学との協働によって活性化され、文学もまた映画との交流の中で変異を遂げてきた。川端康成原作などの“文芸映画”を中心に、アニメ、ミステリー、スリラーなどのジャンルも含め、映画と文学の多様な相関をとらえ直す。
目次
1 ジャンルとメディアの形成(カリガリからドグラ・マグラへ;女性文芸映画というジャンル―その発端と終焉;アニメーションと絵本、児童雑誌の往来―一九五〇年前後における動向より;現代の恐怖、真実の二重化―一九六〇年前後のスリラー映画とその周辺)
2 協働とメディア・ミックス(安部公房の残響―勅使河原宏『サマー・ソルジャー』試論;探偵とノスタルジアの視線―『獄門島』をめぐって;大江健三郎の映画観と小説―『臈たしアナベル・リイ―総毛立ちつ身まかりつ』論)
3 川端康成の小説と映画―パリ国際ワークショップより(川端康成の文学と映画の特性―豊田四郎監督の『雪国』を中心として;「有りがたうさん」をめぐる追走劇;ふたつの『千羽鶴』―映画の宿命に抗して;「文芸アニメ」にとって“原作”とは何か―アニメ版『伊豆の踊子』の脚色;川端作品における映画性の特徴)
著者等紹介
中村三春[ナカムラミハル]
北海道大学大学院文学研究科教授。日本文学・比較文学・表象文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
2
j014、後半はずっと川端康成になるのだが、まあわかりやすいっちゃあわかりやすいかな。個人的には原作料で懐は潤うがプライドはずたずたになるとまで言わしめた昭和に入ってからの文芸映画について読みたかったがどう読んでも一定以上のレベルは越えていて残念ではある、川端原作の映画作品はどれも出来が良さそうだな…。設定の改変にも美学があるというか、過剰なまでの設定も芸術的にまとめられているというか。基本的には理論の本でどう落とし込むことによって映画として成立するかという内容になっていた、まあ戦後の『羅生門』の後かな。2019/02/14