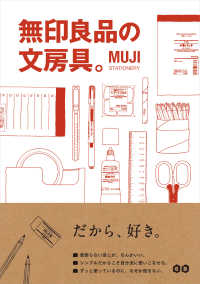内容説明
なぜ足利将軍は戦乱の京都に城を築いたのか?100年に及ぶ二つの将軍家、細川、三好、織田らとの戦いの実像を丹念に追い、足利将軍の戦いと城館との関係を鋭く分析。御所、旧二条城、北白川城塞群をはじめ26城を豊富な縄張り図・現地写真とともに解説。
目次
第1部 戦国足利将軍の激闘(総論1 史料からみる戦国期の将軍の合戦と軍事;足利義澄と足利義稙の軍事活動;義稙政権(第二次)の合戦と軍事
足利義晴期の合戦と軍事
足利義輝期の合戦と軍事
足利義昭期の合戦と軍事)
第2部 足利将軍ゆかりの城館(総論2 戦国期足利将軍の居所と城館;将軍が居所・城館とした場;京都周辺に将軍が営んだ城館;旧二条城の評価;上洛後の足利義昭の城館)
著者等紹介
木下昌規[キノシタマサキ]
1978年生まれ。現在、大正大学文学部准教授。主な業績に、『戦国期足利将軍家の権力構造』(岩田書院、2014年)、『足利義晴と畿内動乱』(戎光祥出版、2020年)、『足利義輝と三好一族』(戎光祥出版、2021年)、『足利義晴』(編著、シリーズ・室町幕府の研究3、戎光祥出版、2017年)、『足利義輝』(編著、シリーズ・室町幕府の研究4、戎光祥出版、2018年)、『足利将軍事典』(編著、戎光祥出版、2022年)などがある
中西裕樹[ナカニシユウキ]
1972年、現在、京都先端科学大学特任准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Abercrombie
3
第1部は戦国期における足利将軍の軍事行動。応仁の乱と同じくらいわかりにくい、明応の政変以後の将軍家、細川京兆家の家督争いから三好家、織田家が台頭してくる流れがよく理解できる。惜しむらくは細川家の系図が第2部に掲載されていたこと。冒頭の足利家の系図と並べておいてくれれば苦労しなかったのに。第2部は【概要】【立地】【歴史と背景】【構造と評価】から成る、足利将軍家ゆかりの城館。期待していた槇島城、岩神館(朽木谷)、平島館、鞆城はパッとしなかったが、堺と一乗谷に詳細図が付いていたのはうれしい驚き。2024/12/04
笑うおそば
0
京都(と周辺)の室町戦国の魅力が分かる本。ともかく、登場人物をサボらずに覚えれば面白くなるのでは?(と思った)足利中心に見た室町戦国期が見えてくるのは新鮮。これくらい分かりにくい時代だと、何回でも見れますね。(未だ判然としないけど)一体、いつこの足利の争いに僕は慣れていくことやら。多分、何十冊も買えばわかるかも。(無理かも)まあ、この本を見れば、京都周辺の何にもない場所の印象が変わるんでしょうな。ああ、あの道、あの城の近くだとか。神社仏閣だけかと思っていたけど、京都の底の深さを知る。2025/06/08