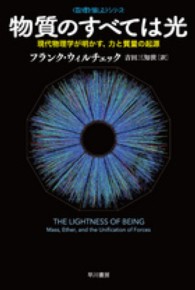目次
城郭研究の進展と織豊系城郭
第1部 織田・豊臣城郭の構造(織豊系城郭の画期―礎石建物・瓦・石垣の出現;織豊系城郭の特質について―石垣・瓦・礎石建物;城郭にみる石垣・瓦・礎石建物;虎口「空間」について;大坂城の縄張り;聚楽第の構造;城郭史からみた聚楽第と伏見城;伏見城と豊臣・徳川初期の城郭構造;破城を再検討する)
第2部 陣城と本支城体制(上平寺城跡の構造―特に元亀元年の改修を中心に;堀尾氏の支城としての三刀屋尾崎城;堀尾氏の支城としての赤名瀬戸山城;堀尾氏の支城としての亀嵩城と三沢城)
第3部 城郭瓦の展開(安土城以前の城郭瓦;小谷城跡出土の瓦について;但馬竹田城跡採集瓦について―文禄・慶長年間築城の考古学的考察;家紋を押印した城郭瓦)
織豊系城郭研究の課題と展望
著者等紹介
中井均[ナカイヒトシ]
1955年大阪府生まれ。龍谷大学文学部史学科卒業。(財)滋賀県文化財保護協会、米原町・米原市教育委員会、長浜城歴史博物館館長を経て、2011年度に滋賀県立大学人間文化学部准教授。2013年度より同教授。2020年度退官。金沢大学、大阪大学などで非常勤講師も務める。専門は日本考古学で、特に中・近世城郭の考古学的研究、近世大名墓の考古学的研究。現在、滋賀県立大学名誉教授。著作多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。