内容説明
将軍の座をめぐる兄弟との激闘、細川高国など大名家に翻弄される幕府。三好長慶ら新興勢力の台頭に、めまぐるしく変わる畿内情勢。没落と上洛を繰り返す苦難の日々の中で、愛息・義輝に託した想いとは!?
目次
第1部 足利義晴と細川高国の時代(父・足利義澄の時代;足利義晴の登場;初期義晴政権とその崩壊;宿命のライバル・足利義維;朽木で行われた政治 ほか)
第2部 帰洛後の政権運営と幕府政治(義晴、帰洛す;特徴的な政権運営;将軍家と大名勢力;将軍家の家政と直臣たち;新たな動乱の兆し;義晴の没落と死)
著者等紹介
木下昌規[キノシタマサキ]
1978年生まれ。大正大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。専門は日本中世史(室町・戦国期)。大正大学非常勤講師を経て、大正大学文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
11
義輝・義昭兄弟の父、足利義晴の評伝。息子たちに比べると地味な扱いの将軍だが、兄弟にしてライバルの義維を四国に没落させ、一時的にも安定政権を築くなど、なかなかどうしてやり手な印象も。ただ畿内周辺の大名による支えが必要という足利将軍家の宿痾は乗り越えられず、細川京兆家の内紛に振り回され、政権の運命は後見役の六角定頼次第という不安定なもの。また将軍が京都にいる意義についても触れており、室町後期の将軍たちが数度の没落を経ても、不屈の闘志で復権を図った理由が垣間見える。2020/10/07
フランソワーズ
6
義輝・義昭の実父義晴の評伝。元来諸大名の上位に立つことで存続した権威であり、権力を行使してきた足利将軍家。室町時代末期の時勢の渦にあって、なんとか永らえてきたという印象が強い将軍・義晴が畿内動乱の中でも存続し得た実像を追う。そこから窺えるのは、己の立場・力量を鑑みて、いかにして動くかを自らの体験をもとに体現した姿。将軍候補義維との競合、細川京兆家の動向、木沢長政や三好長慶の台頭に左右されながらも、六角定頼という協力者がいたことは義晴にとっては幸運であった。→2021/07/31
餅屋
3
義輝・義昭兄弟の父として知られる足利十二代将軍「義晴」の評伝、研究者には「情報量の多い将軍」なのだそうです。復帰現将軍の出奔に伴い、細川高国により擁立されるも京兆家の争いに巻き込まれ没落。京都に将軍が不在となります!義稙流の堺政権に異母兄弟義維が擁立され危機となりますが自壊、正室を近衛家から迎え帰洛し〈足利ー近衛体制〉として安定します。東山に城を造ったり、栄典授与のバラマキでインフレ化したり佐々木六角氏の幕政参加と京兆家に頼らない政治を目指しますが、やはり京兆家の争いに。。。没落先で死去した(2020年)2022/01/06
Toska
3
複雑怪奇な畿内戦国史も、将軍家や三好、六角など様々な視点でなされた研究を追いかけてみると新しいものが見えてくるような気がする。有力大名の在京という室町幕府を支えたシステムが崩壊した応仁の乱後、新たな政権の形を求めて奮闘したのが義晴だった。在国のまま、管領など主要な役職にも就かずに幕府を支えた「協力者」六角定頼の姿は、後の織田信長を彷彿させる。一方、京兆家のゴタゴタは最後まで義晴の足を引っ張ったという印象。2021/10/29
長重
3
[図書館]足利義晴と畿内動乱、読了しました。 細川高国を知りたくて読んだ本でしたが、メインが義晴なので、高国については、それ程詳しく載ってなかったです。 義晴は晴元と仲良しで、成り上がり三好と対立したと思ってのが、晴元と義晴の対立、そこに絡む六角定頼など、新たな知識が多く得られた良書でした😊2021/08/04
-
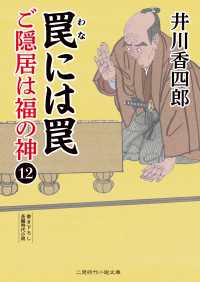
- 電子書籍
- 罠には罠 - ご隠居は福の神12 二見…






