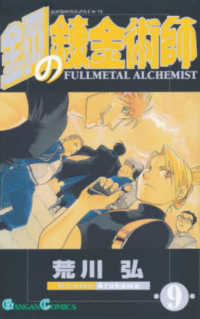内容説明
高千穂宮、オノゴロジマはどこなのか。イザナギとイザナミが廻った柱は、何故「逆」だったのか。なぜ「大八島」と「六島」が産まれたのか。神武天皇の不可解な「迂回ルート」は何を示すのか。そして―富士山は何故消されたのか。『古事記』に記された地はすべてが綿密な計算の元に存在する。一級建築士の精密な研究が導き出す古代の鮮やかなる日本地図。
目次
第1章 伊勢の常浪(伊勢の風景;天孫降臨神話―「日に向かう」夏至日の出‐冬至日没ライン ほか)
第2章 六合の中心(東への旅立ち;大山積神―神武の重要な経由地 ほか)
第3章 国生みの風景(廻る神々;大八島の国生み ほか)
第4章 出雲の暗号(スサノオの道行きと聖軸―八岐大蛇伝説;国引き神話 ほか)
第5章 富士山の幻像(天の浮橋と淤能碁呂島―オノゴロジマの謎;天武天皇の天降り ほか)
著者等紹介
池田潤[イケダジュン]
1957年京都府生まれ。名古屋大学工学部建築学科卒業。建設会社、毛綱毅曠建築事務所を経て、現在、有限会社池田潤建築設計工房主宰。建築家、一級建築士。著書に『朝日の直刺す国、夕日の日照る国―古代の謎・北緯35度21分の聖線』(第三回古代ロマン文学大賞優秀賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とし
6
記紀神話関係の本で、これまで読んだなかで一番面白かった。何度か鳥肌が立ったほど。古代人が太陽ラインを大切にしてたことも、天文学や太陽の軌道について熟知してたということも、もちろん知っていたし、神社が、非常に巧緻な計算によって建てられてるということも知っていたけれど、GPSも精確な地図さえもない縄文時代の日本で、ここまで雄大にして精緻な計算の上で神社が配されていたのかと知ると、あらためて驚かされる。記紀神話がどのように計算されて作られたのかも窺い知れる。このメカニズム、古代人の知恵は、凄いです。2016/06/05
みにみに
3
神話は時間軸や空間軸が分かりにくいなーと思うことがあるけど、その辺をすっきり紐解いてくれた本でした。古事記はいろんな解釈が出来て面白いな。2016/11/12
Tsuchi(TSUCHITANI.K)
0
日立ーーー>日向 太陽のライン2014/11/17
チョイローモンゴル
0
古代人が夏至、冬至の太陽の動きから実に正確に神社を建てそれにちなんだ地名をつけた事に感心。建築士のが書かれてるので目線が新鮮!2012/03/28
まーぼー
0
著者の言葉より→「古事記や日本書紀に記される物語は、単なる思いつきや想像だけで描かれているのではない。そこでは、神話に記される場所を実際にたどり全てを見通した上で、それぞれの場所や地域が語られ、物語が形づくられているのである。」まるでダヴィンチコード。ただのファンタジーだと思っていたから、数々のメカニズムは目から鱗だった。2012/03/21
-
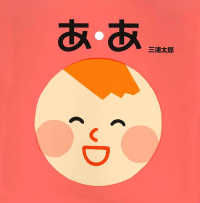
- 和書
- あ・あ