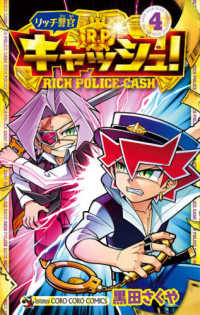内容説明
台湾の新世代作家の一人、徐嘉澤。本作が本邦初訳。一九四七年、二二八事件に始まる台湾激動の頃。民主化運動で傷つき、それまでの生き方を変えなければならなくなった家族。新聞記者の夫とともに、時代の波に飲まれないよう、家族のために生き、夫の秘密を守り続けて死んでいった春蘭。残された二人の息子、平和と起義は、弁護士と新聞記者として民主化とは、平和とは何かを追求する。起義の息子、哲浩は、歴史にも政治にも関心がなく、ゲイだと告白することで一歩を踏み出す。三代にわたる家族の確執を軸に、急激に民主化へと進む時代の波に翻弄されながらも愛情を深めていく一家の物語。
著者等紹介
徐嘉澤[ジョカタク]
1977年、台湾高雄生まれ。国立高雄師範大学卒業、国立屏東師範学院大学院修了。現在、高雄特殊教育学校で教鞭を執りながら、作家活動を行っている。時報文学賞短編小説部門一等賞、聯合報文学賞散文部門一等賞、九歌二百万長編小説コンテスト審査員賞、BenQ華文電影小説一等賞などを受賞。高雄文学創作補助、国家文化芸術基金会補助などの助成を受けた
三須祐介[ミスユウスケ]
1970年生まれ。立命館大学文学部教員。専門は近現代中国演劇・文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
71
近現代台湾史をある一家を主役に。 二二八事件、台北から美麗島事件で高雄に舞台を移し、現代、LGBTやダム問題など。 割と淡々と、リアリスティックに。 比較的若手の作者、祖父が日本人らしい(はっきりしてない)2022/10/21
kum
19
台湾の歴史とともに歩んできた一家三世代の物語。生きる時代や価値観の違いの中で、相容れない父親と距離を置きながらもどこかでその影響を強く受けている息子との複雑な関係性も色濃く描かれる。その複雑さと台湾の辿ってきた道のりは決して無関係ではない。あとがきを読むと著者の父や祖父の姿を投影したと書いてある。「夜が明ければなにもかもが解決するというご都合主義」ではなく真の民主化に向けて歩みを止めないために、タイトルを『次の夜明けに』ではなく不確実性も孕んだ『次の夜明けへ』としたという訳者のエピソードも印象に残った。2025/05/18
星落秋風五丈原
19
台湾で起こった有名な出来事とある一家三代の歴史がリンクしていく。2020/11/15
tokko
9
台湾の歴史には日本を避けて通ることができない、ということがよくわかる。第二次世界大戦終結まで日本の統治が続き、戒厳令、民主化と激動の戦後を迎えることになる。歴史を読めばこういったキーワードを目にするが、そこに住む人々の持つ葛藤、軋轢、摩擦などを理解するのには文学が適している。特に民主化から自由を獲得し、抑圧から解放されているはずなのに、多様性の問題、マイノリティの疎外、いじめ問題、家族の問題など、いろんな課題が噴出するあたりは日本とも共通するのではないだろうか。2024/07/21
ぱせり
6
林家の父たちと息子たちは互いに相手をねじ伏せようと闘うけれど、その闘いはいつのまにか相手を理解しようとする闘いになっていることに気がつく相手を受け容れられなければ自分自身を解き放つことができないのだ。対立する物語の先にあるのは受容、なのかもしれない。作者は、三世代の親子たちの向こうにきっと台湾をみつめている。2020/11/23