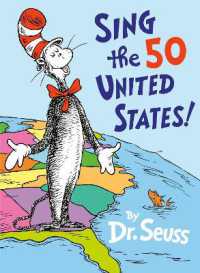出版社内容情報
◎少子化対策の財源は社会保険料への上乗せ?
ますます困窮し、「貧乏くじ」を引かされ続ける若者たち
スリムで効率的な社会保障制度の確立を!
凄まじい勢いで財政が拡大し、バラマキたがる政治家にそれを喜ぶ国民をいう構図が定着してしまった日本。そこに昨今骨子が発表された「異次元の少子化対策」で、おそらく更なるバラマキがなされ、その負担増が若者にのしかかる。
こうした状況から脱却するための対処策はあるのだろうか。「バラマキ政治とクレクレ民主主義」に警鐘を鳴らし続ける著者による、渾身の提言!
<「はじめに」より>
中国の古典の一つ『礼記』に「入るを量りて出ずるを制す」という財政運営の心構えがあるが、現代の日本財政は「入るを量らず出ずるを量らず」の有様である。2012年の予算規模(当初)は90・3兆円だったものが11年後の2023年では24兆円以上増加して114・4兆円にまで肥大化している。2012年は東日本大震災直後、2023年は新型コロナウイルス禍直後と未曾有の危機後という条件では同じであることを勘案すれば凄まじい勢いで財政拡大が進んでいることが分かるだろう。
しかし、日本には糺すべき制度や慣習は野放図な拡大を続ける財政ばかりではない。これまでは高齢世代がバラマキのメインターゲットだったのを、全世代型社会保障の美名のもと、無党派層の現役世代を取り込むべくバラマキ対象が全世代に拡大している社会保障制度もそうだし、働かない中高年を守り「正規」「非正規」という身分制を導入し、そのツケを若者に押し付けているいわゆる日本型雇用慣行もそうだ。
そして今般の新型コロナへの対応も然り。新型コロナは新型であったが故に発生当初は手探りで対応せざるを得ずいま思えば過剰であった点も仕方がないかもしれないが、ある程度データも集まり、守るべき対象が定まったにもかかわらず、相変わらず手探り状態の時の対応が墨守され、一般的に重症化しにくいとされる若者や子どもたちが犠牲にされた。
(中略)
なぜ若者や子どもたちは経済社会全般で貧乏くじを引かされ続けるのだろうか。
本書では若者が引かされる貧乏くじとは何か、その背景や対処策について論じたものである。
(中略)
バラまきたがる政治と欲しがる国民が跋扈する国の仕組みを変え、できるだけの多くの国民が暮らしやすい世の中にするのは、政治家や官僚、専門家だけの責任ではなく、われわれ国民一人ひとりの責務でもある。
内容説明
「異次元の少子化対策」で少子化が加速する?バラマキ政治とクレクレ民主主義。そのツケを払わされる子どもたち。財源調達で実質増税。さらに疲弊する家計、企業。独身、子なしも負担する不公平感。必要なのは社会保障のスリム化。
目次
第1章 財政破綻しなくても財政再建が必要な理由
第2章 財政破綻は国民生活の破綻
第3章 バラマキにNO!と言おう
第4章 少子高齢化時代にふさわしい社会保障制度
第5章 雇用、新型コロナウイルス対策でも貧乏くじを引かされる若者
第6章 若者が貧乏くじを引かないために
著者等紹介
島澤諭[シマサワマナブ]
関東学院大学経済学部教授。富山県魚津市生まれ。東京大学経済学部卒業後、経済企画庁(現内閣府)で、経済分析(月例経済報告、経済白書、経済見通し)、経済政策の企画・立案に携わる。2001年内閣府退官。その後、秋田大学准教授等を経て現在に至る。マクロ経済・財政、世代間格差、シルバー・デモクラシー、人口動態に関するデータ・シミュレーション分析が専門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
- Construction Planni…