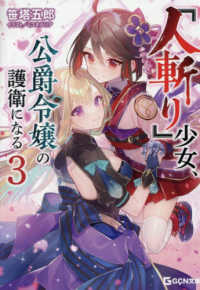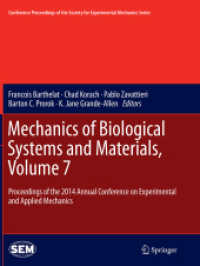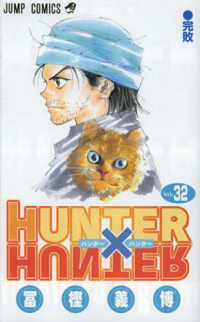内容説明
男は、瓢箪で鯰を抑えているのか?31人の禅僧は何を書いたのか?そして、将軍・足利義持の狙いは何だったのか?日本水墨画の源流・如拙が描いた「瓢鮎図」の謎に迫る。
目次
第1章 賛詩の意味(賛詩を読む;心はとらえられるか ほか)
第2章 賛詩をどう解釈するか(詩作の現場をあきらかにする;大岳周崇 ほか)
第3章 画の意味するところ(どこが目新しいか;男の手の形 ほか)
第4章 「瓢鮎図」のその後(白隠の「鰻のぼり」;白隠が描く「心模様」の絵 ほか)
対談 「瓢鮎図」をめぐって―芳澤勝弘×ノーマン・ワデル(欧米に紹介された「瓢鮎図」;なぜ国宝なのか ほか)
著者等紹介
芳澤勝弘[ヨシザワカツヒロ]
花園大学国際禅学研究所副所長、教授。専門は禅学、禅宗史。近年は、白隠禅画・墨蹟の調査を主なフィールドワークとする一方、室町時代の禅林画賛の解明に力を入れている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
零水亭
10
(2013年、関西移住の際、新大阪駅内の書店にて購入。実際に妙心寺に行けたのは2017年だった。解説と共に絵のコピーが置いてあったが、コピーならば、もうちょい大きい方がよかったなぁ) この本を読むのにはだいぶ骨が折れたが、丁寧に、と言うか、かなり真面目(シンメンボクではなくマジメ)に解説されており、よかった。良心的と感じた。著者の人柄なんだろうか。 五山文学と言うと「詩文(禅僧自身の偈頌や『三体詩』『古文真宝』や蘇軾などの注釈含めて)」を第一に想起するが、「画」「賛」もまたその一つと実感した。2021/02/27
メルセ・ひすい
5
鮎という字は中国ではナマズ、京都妙心寺退蔵院蔵の国宝。禅美術の記念碑的名画。男は、瓢箪で鯰を抑えているのか。31人の禅僧は何を書いたのか。将軍・足利義持の狙いは何だったのか。日本水墨画の源流、如拙…雪舟の師、周文の師が如拙。その国宝「瓢鮎図」の賛詩に着目し、「瓢鮎図」の知られざる本当の意味とは 道元禅師は『正法眼蔵』で一切諸法、万象森羅ともにただこれ一心にして、こめずかねざるのことなし。草木国土これ心なり、…日月星辰これ心なり 山河大地日月星辰、これ心なり 青黄赤白これ心なり 長短方円これ心なりと言うが…2012/12/24
tom
5
「五山文学」というものが高校の教科書に載っていたけれど、内容に何も触れていなかったように思う。ネットで調べても、「五山文学」は意味不明。で、この本は、室町将軍4代目足利義持が禅僧の画家に命令して描かせ、「五山」の禅僧31人に賛を書かせた「瓢鮎図」(国宝の水墨画)を解読するもの。内容としては、禅宗がターゲットとしていた「心」を問うものなのだけど、私が驚いたのは、室町時代の禅僧たちの教養と彼らの文章を読み解く著者の知識の豊富さ。こういう人たちが大昔にも今の時代にもいるのだ。なにやら、ものすごく感動した。2012/11/20
鈴木貴博
3
妙心寺・退蔵院が所蔵する国宝「瓢鮎図」。瓢箪を持つ男と川で泳ぐ鯰、山水と竹の画、上部にある三十一の賛。賛には何が書いてあるのか、絵は何を意味しているのかを読み解き、結局瓢念図は何を意味しているのかを考え、その上で後世の受容をみていく。足利義持その他当時の文化人の豊かな教養の世界、そして禅の世界の奥の深さと面白さの一端に触れることができる。2019/08/20
邪馬台国
3
瓢鮎図は、美術史的に重要な位置づけとして扱われてはいたものの、瓢鮎図に寄せられた31人の画賛の研究が疎かになっていたそうで、その研究を行ったことで見えてきたものをわかりやすく本にしたのがこの一冊。この作品以降も瓢鮎は長い年月モチーフとして描かれてきたそうだが、時代を下るにつれて難読なコンテクストが無視され表面的な絵面だけが伝わっていったというのは面白い。2014/06/11