内容説明
草創期の幕府をまとめあげていたのは、頼朝という個性だった。頼朝と御家人たちとの人間関係の中心には「情」があり、器量ある将軍の下に結集した武士たちは、幕府の未来を素直に信じていた。既存の頼朝像に変更を迫る試み。
目次
プロローグ 物騒な主従漫才
1 流人の生活
2 ドキュメント・鎌倉入り
3 「オレたちの町」鎌倉
4 御家人たちの「溜まり場」鎌倉幕府
5 御家人たちのハートを掴んだ頼朝
6 故郷としての都市鎌倉
エピローグ 鎌倉幕府の青春時代
著者等紹介
細川重男[ホソカワシゲオ]
1962年東京都生まれ。東洋大学大学院文学研究科日本史学専攻修士課程修了、立正大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程満期退学。現在、國學院大學・東洋大学非常勤講師、日本史史料研究会主任研究員。博士(文学)。日本中世政治史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鱒子
52
図書館本。鎌倉幕府は大親分と舎弟たちの 柄の悪い武装集団だった!ざっくばらんな現代語訳がめっちゃ笑えます。歴史上の偉人が血の通った人間であったことを感じました。「高野氏 清水氏の「ハードボイルド読書合戦」で紹介されており、興味を持った本です。2018/05/30
niwanoagata
33
これは笑った 吾妻鏡がベースでそれの訳がめちゃくちゃ面白かった。殺すをバラすとか。「残虐とほのぼの」・「物騒とゆるさ」が非常に当時の様子を想像させてくれてわかりやすい。一般的に頼朝は陰険なイメージと言うのがプロローグにあるがそうなのかな?少なくとも僕はカリスマ的なイメージはあるが陰険さはさほど。当時としてはそんなもんなのかなと。ただ本書のように御家人に親しい存在出会ったのは少し驚いた。これなら家臣がついてくるだろうなと。足利尊氏にせよ。まとめると呉座先生の本並みに笑った。とにかくひたすら面白い。小説並に。2020/05/10
maito/まいと
24
歴史に触れる最もイイ時代、それは過渡期と黎明期、混迷期だ。貴族から武士に主権が移ったその前後を兼任した源頼朝は、もっと注目されてもいい人物(もちろんイメージじゃなくて、その実態を)本書は、将軍を頂点とした中央集権政権を作り、権力維持のために身内や家臣の多くを排除した、頼朝の冷酷な一面の一方で、流人のころから変わらない頼朝の気質と、彼と共に歩こうとした武士との男臭い日々を史実から紐解いていく。まるで学園青春ドラマのようなシーンが随所に出て来るが、大の大人がこんなことホントにしてたのかよ(苦笑)2018/09/29
金吾
23
○鎌倉幕府設立時のキーワードを情で捉えていたのは新鮮でした。どちらかというと陰湿なイメージの頼朝が器は小さく短気で浮気症だけれども憎まれない感じが書かれており、鎌倉武士の蛮族ぶりも相まって明るい時代かなと思わされました。現代語訳の脚色が面白かったです。2024/11/12
くさてる
23
歴史には疎いのですが、Twitterで見かけた抜粋が面白そうだったので手に取ってみたら、あっという間に読んでしまいました。出来たばかりの幕府を支えたのは頼朝と彼を慕う御家人たちだった、というわけで、その関係性や歴史をくだけた現代語翻訳で解説してくれます。笑っちゃうくらいのヤンキー語だったりするのだけど、添えられている原文を読んでみれば、あ、たしかにそんな感じスね……と思ってしまう。そしてそんなヤンチャな武士たちの作り上げていった関係が、こうなったと史実で説明される面白さ。楽しかったです。2020/06/27
-

- 電子書籍
- 30歳までに結婚してなかったら【タテヨ…
-
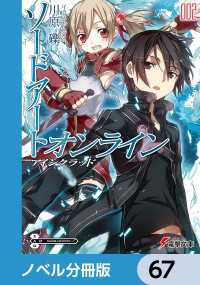
- 電子書籍
- ソードアート・オンライン【ノベル分冊版…
-

- 電子書籍
- 異世界でもふもふなでなでするためにがん…
-

- 洋書電子書籍
-
ポスター発表ガイド
Academ…





