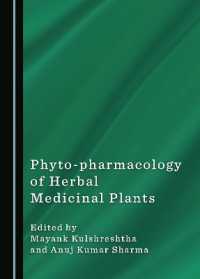内容説明
縄文時代から日本列島では農耕が行われていた。日本の基層文化に雑穀・根栽農耕を発見した名著の復刊。
目次
序章 日本文化を考える(日本文化の基底にあるもの;日本文化分析のための方法論;照葉樹林文化と焼畑農耕文化)
1 縄文農耕論をめぐって―稲作以前に農耕が行なわれていたか(縄文中期農耕論をめぐって;照葉樹林文化と北方系農耕の展開;稲作以前の焼畑農耕)
2 稲作以前の農業(日本の焼畑―稲作以前の生活文化の原型を求めて;東南アジアの焼畑―焼畑農耕文化の源流をたずねて)
3 稲作以前の文化伝統(イモ祭りの伝統;儀絡的共同狩猟の伝統―伝承された稲作以前の農耕儀礼;山の神信仰の展開―稲作以前のカミ信仰;田植技術の発生―稲作以前から以後への農耕技術の展開・その仮説的展望)
4 稲作文化とその基底にひそむもの(稲作文化の問題;稲作文化の基底にひそむもの)
著者等紹介
佐々木高明[ササキコウメイ]
1929年大阪府生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。立命館大学助教授、奈良女子大学教授、国立民族学博物館教授、同館長、アイヌ文化振興・研究推進機構理事長を歴任。国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。専攻・民族学。照葉樹林文化論を中尾佐助とともに構築・提唱(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
25
稲作が始まる前の日本にも焼畑という農耕があった!そして、その名残は今の日本文化にも流れ込んでいるんだ、という結論も刺激的なのですが、一方でそこに至るまでの、五木村や白山の山村、そしてインドやネパールでの実地探査、そして照葉樹林文化を提唱した植物学者や日本文化の多層性を主張した歴史学者、民俗学者との協働の過程がたどれる記述で、とてもわくわくする。71年の出版以降の反響や学説の進展がうかがわれる補注や解説もとてもいい。学問というものはこうでなくては。初音ミクの誕生をたどった本と併読するのにふさわしい本でした。2014/06/15
松本直哉
23
稲作文化論だけで日本のすべてを語った気になることへの違和感を以前から感じていたので本書で大いに蒙を啓かれた。執筆当時の20世紀後半でも日本に焼畑農業をする地域があったのは驚き。狩猟漁撈の縄文と水稲栽培の弥生の間に焼畑農業の雑穀・イモ栽培の文化を想定することで重層的な視点が得られる。インド北部・東南アジア・中国南部から西南日本にいたる帯状の地域(照葉樹林文化)に共通する、定住を避けて山地に住み、少ない人口密度で自然と共生しつつ生きる人々のDNAは、我々の血のどこかにもまだ流れているのかもしれない。 2020/11/04
takao
2
1971年出版の『稲作以前』の復刻版(若干の手直し)。 考古学的証拠がない状況で、縄文時代の栽培植物(焼畑など)を論じた異端の書。 その後の著作 縄文文化と日本人、日本史誕生(集英社 日本の歴史1)、日本文化の基層を探る、日本文化の多重構造 今西研究会:佐々木「今西研究班と照葉樹林文化論」『人類学の誘惑』2010) (関連)照葉樹林文化とは何かp.300 2019/04/08
メーテル/草津仁秋斗
2
まだ弥生時代の水稲農耕が中心に見られていた時代に、縄文焼畑農耕を唱えた画期的な本。東南アジアやインドとの比較も載っており、論理が明解でとても良かった。2015/10/04
k_samukawa
2
名著再び。照葉樹林文化論の主要論者であり、齢八十を過ぎてなお旺盛な活動を続ける学者の鑑・佐々木高明氏の代表的著作の新書化。細かな補注も加えられ、クラシックスとして新たな命を得た、普及の一冊。素晴らしい。洋泉社もいい仕事です!2012/01/04