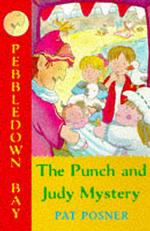内容説明
自閉少女から東大教授へ。その体験の壮絶な記録。自閉症者として異なる価値観をもって優れた朝鮮研究を拓いてきた著者の歩み。いじめ、孤絶、死者・マイノリティへの省察。既存の構造と構造のはざまの疎外された「余白」を源泉として、価値逆転的に展開される独創的な眺望。
目次
1 「自閉的な知」の獲得と構造主義(偶然にも最悪な自閉少女;自閉症者と通過儀礼;「自己スティグマ化」の過程を生きる;与えられる「構造化」/フィードバックされる「構造化」)
2 死者の「かそけきことば」を聴く(死者たちの追憶;死者の声をたずねて;「死の壁」を超える)
3 東アジアの「余白」を生きる(ふたつのハラスメント体験から;東アジアの「余白」に立つ;死者とともなる社会)
著者等紹介
真鍋祐子[マナベユウコ]
東京大学東洋文化研究所教授。1963年北九州市生まれ。奈良教育大学卒業、筑波大学大学院博士課程社会科学研究科修了。社会学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SQT
4
自閉症者として生を受け、自身の扉を開き、近しい人の死を経験するなかで、どのように彼らの気持ちに寄り添い、それを理解し表象することができるか。それは「証言不可能性」に帰着するのだが、それでも自身の謙虚さを持って彼らの歴史を理解しようとすることをやめてはならない…。圧倒された感がある。読むべき本2017/12/08
ぼや
0
ハン・ガンの「少年が来る」で光州事件を知り衝撃を受け、「光州事件で読む現代韓国」からここまでたどり着いた。「誰かが死ぬことと自分が生きていることには何の関係もない」それこそが私が理解できなくて、不思議で許せないような気がすること。死んだのは自分だったかもしれないし、何の尊厳もない無数の死が存在し、私はそれに何ら関わることができない。ハン・ガンが「少年が来る」で生々しく死体を描いたように、ただ目を背けてはいけないのだと思った。全ページ私の頭の中に丸ごと入ってほしいと思うくらい、自分にとって圧倒的な本だった。2022/01/28