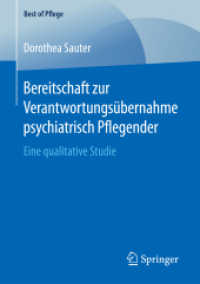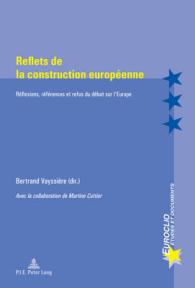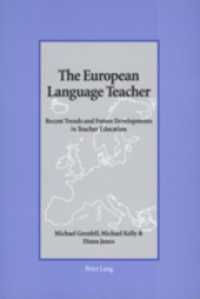出版社内容情報
◎〈文化の生態系〉の歴史と現在を追求する16人の論集。
◎〈イマジネール〉とは、構造化された集団的・社会的想像力のこと。多様な〈文化の生態系〉のなかで作動し、この中で生きる人々の意識や諸活動を突き動かすものとなる。〈エコ・イマジネール〉は、このような想像力の場所的・全体的様相をあらわす概念として造語した。
◎「多様性の科学」としての人類学は、〈文化の生態系〉のうちに作動する〈イマジネール〉の構造と条件を対象化することで、新たな人類知としての〈イマジネール〉への眺望を拓く。
【詳細目次】
文化の見方に関する試論―緒言に代えて(蔵持不三也)
■Ⅰ=カントリーサイドという空間―ハンティングを通してみたイングランドの空間編成の現場(三枝憲太郎)/フリーウェア慣行の文化生態学的研究(松田俊介)/斜めから「文化」を語る―南からの傾度を以て沖縄を記述する試み(前嵩西一馬)/現代日本における「父親論」の問題構成(小堀哲郎)/人が死ぬということ―死生の諸側面とその関係性について(嶋内博愛)
■Ⅱ=異形の修辞学―近世ヨーロッパの怪物譚にみる自己理解としての文化的手法(松平俊久)/参加者の視点から見た聖人祭―聖ロレンソ祭(スペイン・ウエスカ)における「祭りの経験構造」の分析(竹中宏子)/模倣から創造へ―トーテム動物(フランス・ラングドック)の選択にみられる真正感覚の歴史的変化について(出口雅敏)/『ラ・シルフィード』の音楽から― 十九世紀のパリ・オペラ座バレエ団とデンマーク・ロイヤルバレエ団(岡田 彩)
■Ⅲ=幼児教育の中の宗教と日常的慣習―インドネシア・バリ島の儀礼の所作に関する考察(村田敦郎)/「沖縄病」患者の民族誌─ひめゆりの塔と「復帰」にいたる病(北村毅)/中国・羌族桃坪村―その観光化と文化変容(鈴木みづほ)/フィリピン・パナイ島北部汽水域における漁場の利用秩序―定置漁具タバの設置交渉をとおして(小林孝広)/むら持ち網はどのように持続してきたのか―奥能登大敷網漁業の事例から(林陽一)/祟りをめぐる祭祀と魔除けの民俗的メカニズム―コト八日・境界・まれびと(曺圭憲)
【監修者紹介】(蔵持不三也)
1946年栃木県生まれ。博士(人間科学)。現在、早稲田大学人間科学学術院教授。文化人類学専攻。著書に『祝祭の構図』『異貌の中世』『ワインの民族誌』『シャリヴァリ』『ペストの文化誌』。論文・訳書多数。本書序論は監修者が主張してきた「文化の生態系」理論を集約したもの。編者および執筆者は早稲田大学人間科学学術院蔵持研究室およびその周囲から出立した若手研究者であり、その結集によって成った論集。
内容説明
「多様性の科学」としての人類学は、“文化の生態系”のうちに作動する“イマジネール”の構造と条件を対象化することで、新たな人類知としての“イマジネール”への眺望を拓く。“文化の生態系”の歴史と現在を追求する16人の論集。
目次
カントリーサイドという空間―ハンティングを通してみたイングランドの空間編成の現場
フリーウェア慣行の文化生態学的研究
斜めから「文化」を語る―南からの傾度を以て沖縄を記述する試み
現代日本における「父親論」の問題構成
人が死ぬということ―死生の諸側面とその関係性について
異形の修辞学―近世ヨーロッパの怪物譚にみる自己理解としての文化的手法
参加者の視点から見た聖人祭―聖ロレンソ祭(スペイン・ウエスカ)における「祭りの経験構造」の分析
模倣から創造へ―トーテム動物(フランス・ラングドック)の選択にみられる真正感覚の歴史的変化について
『ラ・シルフィード』の音楽から―十九世紀のパリ・オペラ座バレエ団とデンマーク・ロイヤルバレエ団
幼児教育の中の宗教と日常的慣習―インドネシア・バリ島の儀礼の所作に関する考察
「沖縄病」患者の民族誌―ひめゆりの塔と「復帰」にいたる病
中国・羌族・桃坪村―その観光化と文化変容
フィリピン・パナイ島北部汽水域における漁場の利用秩序―定置漁具タバの設置交渉を通して
むら持ち網はどのように持続してきたのか―奥能登大敷網漁業の事例から
祟りをめぐる祭祀と魔除けの民俗的メカニズム―コト八日・境界・まれびと
著者等紹介
蔵持不三也[クラモチフミヤ]
1946年栃木県生まれ。博士(人間科学)。早稲田大学人間科学学術院教授。専攻は文化人類学
嶋内博愛[シマウチヒロエ]
早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程修了、ドイツ・フライブルク大学博士課程(ドイツ民俗学主専攻)退学(2000年)、博士(人間科学)(早稲田大学、2004年)。早稲田大学人間科学部助手などを経て、東京大学大学院人文社会系研究科次世代人文学開発センター客員研究員。専攻は文化人類学・ドイツ民族学
出口雅敏[デグチマサトシ]
1969年生まれ。早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。早稲田大学人間総合研究センター助手を経て、駒澤大学、東京家政学院大学、女子栄養大学、聖学院大学非常勤講師。専攻はフランス民俗学
村田敦郎[ムラタアツロウ]
1972年、大阪府生まれ。早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。共栄学園短期大学社会福祉学科児童福祉学専攻助教。専攻は文化人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。