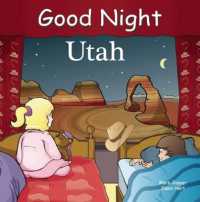目次
「くず屋」という仕事
くず屋さん事始め
拾って生きることのできない社会
協同組合に何ができるのか
「障がい者」と共に働くということ
「身体仕事」で人も地球も健康に!?
わが家のごみは生態系につらなっている
天ぷら油のリサイクルが教えてくれた
紙のリサイクルも持続可能な地域循環型にしたい
使い捨てを止めて気候変動を防ぐ
SDGsと廃棄物と地球サミット
食べられるモノが捨てられている
ペットボトルと砂漠の水
「時給22円」の使い捨て―ファストファッションの向こう側
介護の日々と遺品整理
稼ぐことと働きがい
福島から「フクシマ」への旅 2011~2018
千年のごみ、万年のごみ
濃密な経験―生き方を育て合った共同保育
「戦争を知らない子どもたち」から「戦争を知らない孫たちへ」
若きミニマリストたちへ
未来との対話
くず屋の四季
著者等紹介
東龍夫[ヒガシタツオ]
1952年、東京都生まれ。(有)ひがしリサイクルサービス代表、札幌市資源リサイクル事業協同組合理事長、日本再生資源事業協同組合連合会副会長。1979年以来、集団資源回収、廃棄物再生事業(古紙・ビン・缶・金属・廃食油・古布)、再生原料を利用したエコ商品の販売などを行うとともに、北海道のさまざまな社会運動に積極的に関わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sakie
16
札幌市資源リサイクル事業協同組合の理事長を務めた方で、資源リサイクル業を長年手掛けていただけではない、障害者雇用、農産物廃棄、原発問題などの社会活動も多岐に携わり、ここまで長く幅広く自分の言葉で語れる人に私は出会ったことがない。"くず屋"だから見える重たい様々も、説明する口調は優しいのだ。豆腐屋さんで買った豆腐を腐らせたとき、申し訳ないと思う。スーパーで買った豆腐を腐らせたとき、損したと思う。なぜだろうね、と。知りたかった廃棄やリサイクルの実際と共に、思いがけず「なつかしい未来」への魂も受け取りました。2021/03/06
魚京童!
11
要は言い方、見方だよね。環境に配慮して、持続可能で、自然に優しい社会を作りましょうって大量生産、ネット社会、資本主義とは相いれていない。ただそれだけ。どこで線引きをするか。どこまで許容できるか。妥協ではない、これは政治だ。まつりごと。世界が大きすぎて私には対応できないだから諦めてしまう。どうでもよくなってしまう。すべてにやりようはあるのだろうが、やる意思を持つのかどこまで戦うかっていう話だよね。どうでもよくなってしまえば世界はそれまで。幸せな新世界。ぐうたらできる新世界。新世界へようこそ!2023/02/12
Carol
2
元々バラバラに書かれたものをまとめて加筆したものだそうで、話が飛んでいるように感じて私にはちょっと読むのが大変でしたが、自分の今の生活がいかにSDGsに反しているかを認識することができました。一人一人は小さなことしかできない。けれど、それを「する」ことが大事なんだ。2019/12/30
buchiand(ブチアンド)
1
紙、瓶、缶、ペットボトル、服、放射能汚染物質、食品などなど…色々なものの廃棄について知ることができる良い本でした。筆者のバイタリティーがすごい!読みやすく、勉強になりました。2021/09/19
Keiko Yamamoto
1
非常に深いいい本だった。 私たちが出すゴミの種類、分別、その後の処理、そして環境負荷、そしてエネルギー問題から経済問題へ。 ゴミは処理をする際のことだけを考えるのではなく、生産⇒廃棄⇒その後の行方(自然に還元されない)までを一連の流れとして考えなければならない。 何万年も自然の中に異物として残り続けるごみを生産して、人間は何をしているのか? 私たちは考えるべきときに来ている。2020/08/20
-

- 洋書
- RESET
-
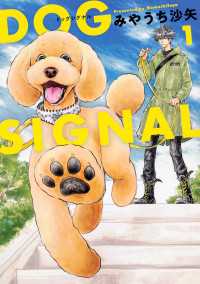
- 電子書籍
- DOG SIGNAL【タテスク】 Ch…