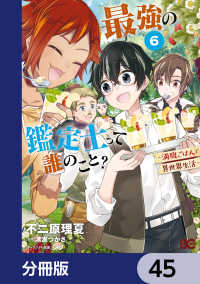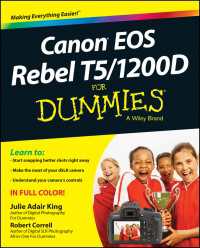出版社内容情報
「地の果て」の、さらなる果てのトポスへの旅の意志。
「地の果て」を、今ここに接続する獰猛で繊細な想像力。
いま、小説はいかに可能か。壮大な物語世界を背景に、現代文学の異形の巨人が語る小説作法。
著者絶頂期の表題作と、同時期の発言「音の人 折口信夫」「坂口安吾・南からの光」を増補した、没後30年記念改訂版!
内容説明
「地の果て」の、さらなる果てのトポスへの旅の意志。「地の果て」を、今ここに接続する獰猛で繊細な想像力。いま、小説はいかに可能か。壮大な物語世界を背景に、現代文学の異形の巨人が語る小説作法。著者絶頂期の表題作と同時期の発言「音の人 折口信夫」、「坂口安吾・南からの光」を増補した、没後30年記念改訂版!
目次
現代小説の方法(小説を阻害するもの;主人公について;構造について 場所について)
ワープする物語の魅力
三島由紀夫をめぐって
音の人 折口信夫
坂口安吾・南からの光
エスパース・デポック図書館 中上健次氏の本棚―物語/反物語をめぐる150冊
著者等紹介
中上健次[ナカガミケンジ]
1946~1992年。小説家。『岬』で芥川賞、『枯木灘』(毎日出版文化賞)など
〓澤秀次[タカザワシュウジ]
1952年生まれ。文芸評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ノブヲ
20
東京堂書店主催、中上健次による「小説教室」。その講義録。全四回。主たる目的は小説の書き方を教授するということになろうが、もちろんそれだけに収まるはずもなく。受講者の期待に応えるという意味で中上健次のサービス精神もあるだろうが、冒頭つい五日前までアフガン紛争中のパキスタンはペシャワールに滞在していたということを話の糸口にする。このことで教室は一気に砂漠のど真ん中に連れて行かれたようなイメージに貫かれる。背後で銃声の鳴り響く炎天下の漂流教室。こうしてまたひとつ新たな神話が捏造される。後は推して知るべし、だ。2025/08/22
amanon
11
講演集ということでサクサク読めるが、しかし、スッと飲み込めるようなものでは決してない。著者自身、喋りが下手だと言っているように、流暢とは言い難い語りのうちに、表には現れてこない重層的な何かが潜んでいるように思われ、本来ならそこを注意深く読み込んでいく作業が必要ではないか?と思わされる。とりわけ興味深く思えたのは、やはり車についてのくだり。ネットやスマホの時代に、このような言述はどれだけの説得力を持つのか?しかし、この観点から小説を改めて論じることには意味があるのかも。未消化感強いので、再読が必要かも。2022/11/20
読書メーターJr.
1
この人は物語の中に親と子のメタファーを感じられないと駄作と判断するんだろうか。移動がなければただの心理劇になるという考えは納得。人間はどこまでいっても肉体的だから創作において身体性は必要なんだろう。蛇や音のような定住できないものはワープして突然物語の中にやってこさせられるというのも、移動の観点から考えると興味深い。逆に机とか動かないものが急に現れても面白いけれど。用は無意識で理解している常識を利用せよということなのかな。正直難しくてほとんど斜め読みになってしまったけれど、得られるものはそれなりにあった。2024/09/02
readerr
1
作家の思いがほとばしり、かと思うと聞き手が困惑するような深淵に入ってしまう、つまり、講演というより本人の素が現れた一人語りのようである。主人公は私生児であるべき、神聖な場所としての路地、神話的な仮母と言った言葉から、彼の凝縮していくエネルギーと世界観のあり場所が感じられる。現代の読者にこうした感覚がどのように受け取られるのだろう。かって、彼の小説を読んだ者としては、久しぶりに会って懐かしいというより、遠い昔という感じがするのだ。2023/03/30