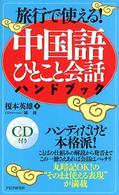内容説明
観光、SNS、移民、テロ、モバイル、反乱…新たな社会科学のパラダイムを切り拓いた、『社会を越える社会学』を超える“移動の社会学”の集大成。
目次
第1部 モバイルな世界(社会生活のモバイル化;「モバイル」な理論と方法;モビリティーズ・パラダイム)
第2部 移動とコミュニケーション(踏みならされた道、舗装された道;「公共」鉄道;自動車と道路になじむ;飛行機で飛び回る;つながる、想像する)
第3部 動き続ける社会とシステム(天国の門、地獄の門;ネットワーク;人に会う;場所;システムと暗い未来)
日本語版解説 アーリの社会理論を読み解くために
著者等紹介
アーリ,ジョン[アーリ,ジョン] [Urry,John]
1946年、ロンドン生まれ。ランカスター大学社会学科教授(distinguished professor)、英国王立芸術協会のフェローなども併任。21世紀における「移動」をめぐる新たな社会科学の中心的人物として、世界的に著名
吉原直樹[ヨシハラナオキ]
1948年生まれ。慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了。社会学博士。東北大学名誉教授。大妻女子大学社会情報学部教授
伊藤嘉高[イトウヒロタカ]
1980年生まれ。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。山形大学大学院医学系研究科講師(医療政策学講座)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
センケイ (線形)
3
広範でやや気障な論調ゆえかやや言葉の使い方の怪しい所もあるが、逆に言えば広範な勘所が得られ、興奮させられる本ともいえるだろう。左のような前提付きでいうなら、鉄道や航空機の登場による社会の動態の変化、情報空間と実空間があいまいに溶け合う変化、そして複雑性の議論をも範疇にいれようと模索する試論、そしてこれらを束ねる「移動」という空間の定義から目が離せない。これから新たな議論を積み上げる足掛かりあるいは考え方のヒントとして活きてくるのではないだろうか。2019/01/31
ぷほは
3
アーリの本をまともに読むは確かこれが始めてなのですが。なんかパワポの資料をそのまま文章化したような本で読書の面白味がないためプロの読書家は序論と終章のみでいい。逆にⅠ部と2部は学部生2~3回向けの文献案内も兼ねた親切さはある。シリーズ/ネクサスのシステム差異をそこまで説明する気ない割にシステム概念を乱用しすぎてネットワーク論との噛み合わせがない、定住についてハイデガー、徒歩についてワーズワースに頼りすぎ、時間論についてレヴィ=ストロースに触れてないのは致命的など。が、IoT関連の自動車論は先見の明がある。2018/02/22
かぺら
1
社会科学のパラダイムとして提示しているためシステム論だけでなく義務論からも"移動"を論じており、かなり裾野が広い。多角的に論じている反面、理論部分での曖昧さは結構あるような気がしている。移動の分類とかも結局なんで12個である必要があったのだろう(僕が全然読めてないだけなのかもしれないが)主に第2部の各移動の歴史的展開や現在の考察などは鮮やかな切り口でかなり面白いと思った。 2019/09/17
S.Taoka
1
世界で起こっている/起きた出来事を「移動」という切り口でどう解釈できるか、定義から具体例まで広くカバーしていて分厚いのが頷ける。しかし「移動」の定義が想像以上に広く、「常に静的でないものの全て」と言ったほうが正しいレベル。一気に隈なく熟読するようなものではなく、研究・生活の中で時折立ち返りたい本。2019/04/25
maki
1
移動は手段だと思ってきた私にとって新鮮でした。工業デザインで馴染み深いアフォーダンスを道に対して用いているところに、その先の可能性を感じた。2018/11/14
-

- 電子書籍
- 傾国のカルマ 29 UPコミック
-

- 電子書籍
- 休み時間の生物学 休み時間シリーズ