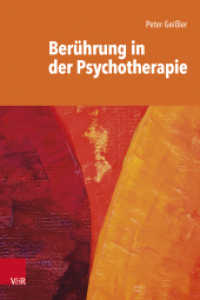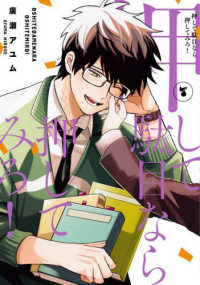内容説明
理性の働きとその限界を明確にし近代哲学の源泉となったカントの主著、厳密な校訂と判りやすさを両立する待望の新訳。
目次
1 超越論的原理論(超越論的感性論;超越論的論理学)
2 超越論的方法論
著者等紹介
熊野純彦[クマノスミヒコ]
1958年、神奈川県生まれ。1981年、東京大学文学部卒業。現在、東京大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんすけ
18
改めて日数をかけて読む書として認識した。ただし中断も許されない、日を空けることなく読み続けることで真意が把握できる書でもあった。 空間と時間が、人間の認識のもとに存在することを明確にした書ではあるが、カントの道徳観が理性のもとに確立した書でもあった。本書の最後にしてカントは道徳を問い、己の真の途にその所在を語る。 こればかりは間を空けずに読み続けなければ、理解は不可能ではないだろうか。 『純粋理性批判』に接して六十年近い歳月が流れたが、漸く真意に近接した感があり、感慨深い五十日を超す日々となった。2023/12/13
てれまこし
3
今まで読まずに済ませていたが、結局読まされる羽目になった。予想通り難しくて、何のために読み始めたか忘れるくらいだった。知を得るためには、知られるものだけじゃなく知る者が自らも知らなければならない。そして、知は知の客体に対する力を意味するだけではなく、知の主体そのものを変容する。そうだ、人文教育の効能を求めてこんなものを読む羽目になったのだった。再帰性というのはヘーゲルが元祖かと思ったのだが、どうもカントがそれに先駆けている。また宿題が増えた。なお、カントのアーレントへの影響を確認するという副産物もあった。2018/05/10
Yasunori Hosokawa
2
圧巻。多分再々読くらいで前回までは岩波文庫版だったのですが、これぞ近代哲学の頂点、という思いを新たにしてしまいました。神秘的、あるいは叡智的な領域へ思弁が踏み込むことを厳に慎むことが逆に理性の権威を復活させるのだ、という姿勢は、ソクラテスの「無知の知」とも似てますが、哲学というものが何であるのかを近代において精緻に再現してみせた、という風に自分は読みました。2025/05/13
有智 麻耶
2
猫町倶楽部の読書会で、半年間かけて何とか読み切ることができた。〈感性/悟性〉や〈現象/物自体〉などの二元論を打ち立てながら、いわば人間の認識の手が届く範囲を画定しようとした超越論的哲学である。後半の「超越論的方法論」は、概説書ではほとんど紹介されていないが、どのような研究が蓄積されているのか気になった。翻訳についていうと、漢字→仮名の開き方に癖があるため、読みにくさを感じる読者はいるだろう。2024/07/24
かずりん
2
前回挫折で再読。理性の限界を見極めることで、神は存在するか等、人間は答える能力がないことをを論証しようとする。純粋理性の本来の課題は、アプリオリ(経験に基づかないという意味)な総合判断はどのようにして可能かとの問いを明らかにすることだと云う。数学と物理学の例をあげて総合判断を示し、形而上学も同様とする。例えば物理学の質量保存の法則が、相対性理論では様々な形態のエネルギーに転換していき、これに適応せず理論に無理があるように思う。とはいえ科学や数学の研究成果を哲学に取り入れんとする積極的な姿勢に圧倒される。2021/04/25
-

- 和書
- 自然が答えを持っている
-
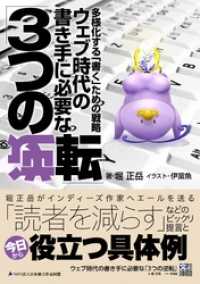
- 電子書籍
- ウェブ時代の書き手に必要な「3つの逆転…