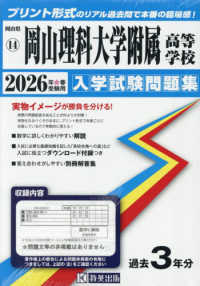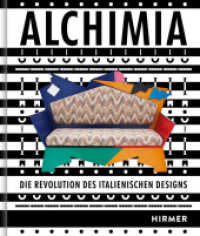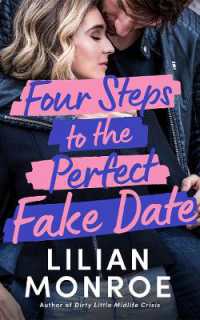- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
内容説明
一九三〇年代、若き芸術家たちに熱狂的に支持されたシュルレアリスムの衝撃から展開、最盛期、弾圧、戦後まで。日本の美術史への影響を約90名の絵画や豊富な資料、テキストでたどる。最新研究の集大成!
目次
序章 シュルレアリスムの導入
第1章 先駆者たち
第2章 衝撃から展開へ
第3章 拡張するシュルレアリスム
第4章 シュルレアリスムの最盛期から弾圧まで
第5章 写真のシュルレアリスム
第6章 戦後のシュルレアリスム
著者等紹介
速水豊[ハヤミユタカ]
三重県立美術館館長
弘中智子[ヒロナカサトコ]
板橋区立美術館学芸員
清水智世[シミズトモヨ]
京都府京都文化博物館学芸員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koke
13
巻末の論考は未読。なので的外れかもしれないが、福沢一郎と瀧口修造が検挙され美術文化協会が「国策に沿って活動を継続することを表明する」という流れに少々落胆した。たぶん、日本のシュルレアリスムはブルトンの考えたものとは別物だった。つまり「理性によって行使されるどんな統制もなく、美学上ないし道徳上のどんな気づかいからもはなれた思考の書きとり」ではなかった。厳しいことを言えば、抽象という別のモードともゆるっと結びついてしまうような、ひとつのモードにすぎなかったのではないか。そういう目で個々の作品にあたりたい。2025/06/22
しゅん
10
戦争の日本への影響など、手堅く役立つ論文を含む。1930年代のシュルレアリスム需要に、イギリス詩学の文脈が重要な枠割を果たしたという話が面白い。2024/06/04
たろーたん
0
覚書。三岸好太郎「海と斜光」、飯田操朗「婦人の愛」、六條篤「らんぷの中の家族」、斉藤長三「わが旅への誘い」、福沢一郎「人」、米倉壽仁「ヨーロッパの危機」、伊藤久三郎「振子」、小牧源太郎「民俗学系譜」、北脇昇「独活」、森堯之「風景」、寺田政明「生物の創造」、浅原清隆「多感な地上」、伊藤研之「音階」、桂ゆき「土」、長末友喜「季節の貢」、多賀谷伊徳「飛翔する前」、吉川三伸「葉に因る絵画」、吉沢岩美「女幻」、堀田操「断章」、高山良策「矛盾の橋」2024/10/08
analjustice
0
板美の展覧会の復習として2024/03/06
-

- 電子書籍
- 焼いてるふたり(1)