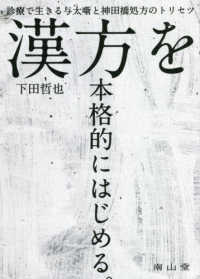内容説明
食の流行は、時代を反映します。食の背景には必ず時代の状況があり、そのときの政治体制、経済的な環境が食文化に及ぼす影響は大きい。江戸時代を皮切りに、開国後、外国との交流が活発になりメディアが発達する時代。外からの刺激を受けて流行が生まれ、文化が発展していく様子を解説します。食のトレンドにとどまらない、私たちの生活に結びついた新しい歴史や社会の視点が見えてくる。
目次
第1章 幕末と「獣肉食」ブーム
第2章 あんパンに始まる、日本の菓子パン・総菜パン
第3章 大正時代の「三大洋食ブーム」
第4章 戦後~高度経済成長期の「台所革命」
第5章 キッチンと料理の関係
第6章 一九七〇年代、外食のトレンドと女性たちの変化
第7章 一九八〇年代、「エスニック」料理ブーム
第8章 デパ地下の誕生と「男女雇用機会均等法第一世代」
第9章 平成のスイーツブーム
第10章 パンブーム―日本人とパンの新しい関係
第11章 韓国料理の流行から見えてくるモノ
第12章 「食ドラマ」の変遷に見る時代の変化
第13章 令和に起こったご飯革命
著者等紹介
阿古真理[アコマリ]
作家、生活史研究家。くらし文化研究種主宰。1968年、兵庫県出身。食や暮らし、ジェンダー問題等をテーマに執筆。2023年、第七回食生活ジャーナリスト大賞ジャーナリズム部門受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。