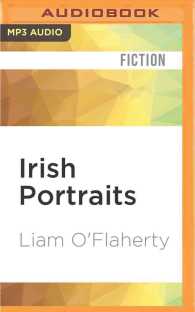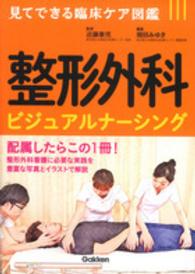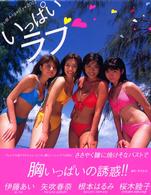内容説明
平均年齢80近く、高齢化率89%の集落。それでも「限界」とは言わせない。日本滞在25年のアメリカ人が愛する田舎の幸せな暮らし―。南日本新聞人気連載「小組合長日記」他を収録。
目次
1 初めての小組合長―2006~2007(里村を見つけて;幹男さん;力をあわせて ほか)
2 深呼吸―2007~2009(アメリカへ帰る;周防大島;キャンプ ほか)
3 再び小組合長に―2009~2010(私ができること;透き通った空;種イモ ほか)
著者等紹介
アイリッシュ,ジェフリー・S.[アイリッシュ,ジェフリーS.][Irish,Jeffrey S.]
1960年米国カリフォルニア州生まれ。1982年、エール大学を卒業後、清水建設に入社。三十代より下甑島で定置網の仕事に就き、その後ハーバード大学大学院と京都大学大学院で民俗学を専攻。1998年より鹿児島県川辺町に移り住み、土喰集落の小組合長を2回務めた。日々の生活や田舎暮らしなどを南日本新聞に9年間連載。日本の知識人、梅棹忠夫や加藤周一などのインタビュー記事を英字雑誌に掲載。2010年から鹿児島国際大学の准教授として、地域創生、まちづくりなどについて教えている。2010年度南日本文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。